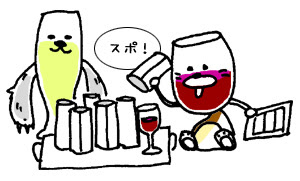2018/05/30
第2回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト予選 受けて来ました!
第2回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト予選に行ってきました。
日時:2018年5月30日(水)
場所:ホテル雅叙園東京
<スケジュール>
14:00 ~ 14:30 受付
14:30 ~ 14:40 入場
14:40 ~ 14:45 オリエンテーション
14:45 ~ 15:15 テイスティング(30分)
参加者は200~300人くらいいたでしょうか。
広い会場でほぼ満席でした。
■禁止事項
会場に一旦入ると、再入場はできません、事前にトイレに行っておきましょう。
もちろん入るときに注意事項としてアナウンスされます。
本日は夏日で蒸し暑かったのですが、会場は冷房がしっかり効いていて、上着をクロークに預けたことを少し後悔。
ただ、試験時間は短いので寒くて震えるって感じではなかったですね。
会場内で携帯電話やスマホを使ったら即退場で、もちろん撮影もNG。
掛け時計はないので、時間が気になる人は腕時計していった方がいいかもですね。
終了5分前にはアナウンスがあります。
入場時にグラスにお酒は注がれている状態ですが、匂いを嗅いだり触ったら退場です。
■回答項目
撮影はNGなので、記憶にある範囲です。
違っているかもしれませんので、ご容赦ください。
<ワイン>
・主要品種
・生産年
・生産国
・生産地区
・販売価格
を直筆で記入、カタカナでも現地の言語でもOK。
<日本酒>
・主要品種
・特定名称
・生産県
・固有名称
・精米歩合
・アルコール度
・販売価格
だったと思います。
<リキュール>
・主要品種
・生産国
・生産地区
・固有名称
・アルコール度
・販売価格
だったような・・何か足りないような気も。。
■解答
あくまで私の解答なので、正しい答えではありません。
というか、たぶん違ってます。。
◇白ワイン①
こってりしたリッチで樽香のあるタイプ。
果実味も甘みもあって、ニューワールドの印象。
さすがにコンテストにシャルドネは出ないだろうと最初は思ってましたが、一周回って出るかも、と考えを切り替え、日本のシャルドネを選択。
登美の丘をイメージして、シャルドネ 日本 山梨 3500円と解答。
◇白ワイン②
外観は淡めで、香りがアロマティック。
イメージとしてはゲヴュルツトラミネールやヴィオニエ、トロンテス。
甘みもあるけど、かなり酸味が強く、ニューワールドというよりはドイツワインっぽい印象。
これは、アルザスのゲヴュルツトラミネールを選択。
終わってから考えると、ドイツワインって選択肢もあったかも・・
◇赤ワイン①
野趣あふれるワイルドな香りのタイプで、少なくともグローバル品種ではなさそう。
テンプラニーリョとか、カベルネ・フランをイメージしたけど、味わいはまろやかで甘味がありニューワールドの印象。
アメリカっぽさを感じたので、アメリカらしい品種ということでジンファンデルをチョイス。
産地は良くわからないので、とりあえずカリフォルニア。
◇赤ワイン②
フォクシーフレーヴァーがあり、日本の品種に絞る。
前回のソムリエ協会セミナーで「ヤマ・ソーヴィニヨン」なんて出ましたが、さすがにそれはないだろう・・と思い除外。
マスカット・ベーリーAにしては、ちょっと野性的、かと言ってキャンベル・アーリーほどのフォクシー感でもない。
過去一度飲んだことのある、「ツヴァイゲルト・・なんとか」みたいなやつがイメージが近いかも・・・と一生懸命思い出してみるものの、正確な名前を思い出せず、まあいっか、と「ツヴァイゲルトベーゼ」と記入。
終わってから調べてみると「ツヴァイゲルトレーベ」が正解・・・
かなりチャレンジングな選択だったけど、品種名を間違えて撃沈です。
◇日本酒
素直でまろやかスッキリと美味しいタイプでしたが、醸造用アルコールが入っている印象だったので、純米ではない吟醸を選択。
精米歩合は50%と記入したのですが、吟醸の精米歩合って60%でしたね。
これも完全にアウトですね。
使用米はまったく分からないので最初に「愛山」と記載したものの、安全をみて「山田錦」に変更。
北の方の安定感のある印象と勝手に想像して、新潟の八海山にしておきました。
選択ではなくて記入方式なので、漢字が簡単なやつで。。。
◇醸造酒
これはもう「グラッパ」しかない、という味わい。
トスカーナのスーパータスカンあたりのグラッパをイメージして、生産地区は「トスカーナ州」使用品種は「サンジョヴェーゼ」売値は5,000円と回答しました。
で、終わってからハッと気がついたのですが、ひょっとしてこれは国産のグラッパ??
最近日本でもグラッパが作られてるみたいですからね~。
簡単じゃんと思ったけどひっかけ問題だったかも。
■まとめ
決勝進出者の結果発表は6月8日らしいのですが、出題品種等は公表されないようです。
ちょっと残念。。。
でも静かな試験会場で、あれこれ推理して回答を導き出すのは日常生活から離れた空間で、とても楽しかったですね。
また機会があったら受けてみたいですね。
■正解発表ありました!
予選通過の発表に合わせて、正解発表がありました。
残念ながら予選通過はしませんでしたが、これだけ外せば当たり前ですね。
ワインエキスパート試験に出るような、いわゆる主要品種はありませんね。
面白いラインナップです。
ジョージアのワイン、飲んどかないと。。。
◇白ワイン①
主要品種:シュナン・ブラン
生産年:2015
生産国:南アフリカ
生産地:パール
◇白ワイン②
主要品種:ルカツィテリ
生産年:2015
生産国:ジョージア
生産地:カルトリ
◇赤ワイン①
主要品種:カルメネール
生産年:2016
生産地:チリ
生産地:カチャポアル・ヴァレー
◇赤ワイン②
主要品種:ツヴァイゲルト・レーベ
生産年:2015
生産国:日本
生産地:長野県(塩尻市桔梗ヶ原)
◇日本酒
主要品種:五百万石
特定名称:吟醸酒/特別本醸造酒
生産都道府県:新潟県
アルコール度:15%
精米歩合:55%
◇醸造酒
使用品種:フランボワーズ/ラズベリー
タイプ:ブランデー/オー・ド・ヴィー
生産国:フランス
生産地:アルザス
アルコール度数:40%
2018/03/30
第2回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテスト 申し込みました
第2回J.S.A.ブラインドテイスティングコンテストに申込みました!
https://sommelier.jp/topics/view/20180530_btc2
<開催概要>
■開催日
2018年5月30日(水)
■会 場
全国7会場[札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡]
■出場資格
予選開催日において年齢20 歳以上の方。国籍、職種、経験は不問。
■参加料
会員・賛助会員:1,000 円 一般:10,000 円
■スケジュール (予定)
14:00 ~ 14:30 受 付(※14:30まで入場はできません)
14:30 ~ 14:40 入 場
14:40 ~ 14:45 オリエンテーション
14:45 ~ 15:15 テイスティング(30分)
(タイムスケジュールは変更する場合もありますので予めご了承ください)
全国の成績上位者より10名前後選出
■申込締切
2018年4月27日(金)まで
■公開決勝
2018年10月愛知にて開催予定
優秀者には賞状と副賞が授与されます。
<第1回の出題品種>
https://www.sommelier.jp/topics/view/20170511btc_yoseninryo
◇ ワイン ◇
1)
シャルドネ
2014年
チリ:カサブランカ・ヴァレー
2)シラーズ/シラー
2015年
オーストラリア:アッパー・ハンター・ヴァレー
3)
ガメイ
2012年
フランス:ムーラン・ア・ヴァン
4)
グルナッシュ
2015年
南アフリカ:スワートランド
これに加えて、生産者と価格も出題されたようですね。
◇ その他お酒 ◇
5)
ヴァン・ド・リキュール
フランス:コニャック
アルコール度:17%
6)
芋焼酎
日本:宮崎県
アルコール度:44%
これに加えて、商品名と価格も出題されたようです。
ワインエキスパートコンクールのように撃沈すること必至ですが、参加することに意義があると思ってチャレンジしてみたいと思います。
https://sommelier.jp/topics/view/20180530_btc2
<開催概要>
■開催日
2018年5月30日(水)
■会 場
全国7会場[札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡]
■出場資格
予選開催日において年齢20 歳以上の方。国籍、職種、経験は不問。
■参加料
会員・賛助会員:1,000 円 一般:10,000 円
■スケジュール (予定)
14:00 ~ 14:30 受 付(※14:30まで入場はできません)
14:30 ~ 14:40 入 場
14:40 ~ 14:45 オリエンテーション
14:45 ~ 15:15 テイスティング(30分)
(タイムスケジュールは変更する場合もありますので予めご了承ください)
全国の成績上位者より10名前後選出
■申込締切
2018年4月27日(金)まで
■公開決勝
2018年10月愛知にて開催予定
優秀者には賞状と副賞が授与されます。
<第1回の出題品種>
https://www.sommelier.jp/topics/view/20170511btc_yoseninryo
◇ ワイン ◇
1)
シャルドネ
2014年
チリ:カサブランカ・ヴァレー
2)シラーズ/シラー
2015年
オーストラリア:アッパー・ハンター・ヴァレー
3)
ガメイ
2012年
フランス:ムーラン・ア・ヴァン
4)
グルナッシュ
2015年
南アフリカ:スワートランド
これに加えて、生産者と価格も出題されたようですね。
◇ その他お酒 ◇
5)
ヴァン・ド・リキュール
フランス:コニャック
アルコール度:17%
6)
芋焼酎
日本:宮崎県
アルコール度:44%
これに加えて、商品名と価格も出題されたようです。
ワインエキスパートコンクールのように撃沈すること必至ですが、参加することに意義があると思ってチャレンジしてみたいと思います。
2018/03/02
2018年ソムリエ協会例会セミナー「テイスティングのコツ」
ひさしぶりにソムリエ協会例会セミナーに出席してきました。
実践的な内容で、明日からでも使えるようなテクニックやコメントのノウハウ、さらに8種類の美味しいワインが飲めて、とても充実したセミナーでした!
■セミナー概要
開催日:2018年2月27日(火)14:00~16:00
会場:横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 5F宴会場「 日輪」
講師:森 覚 ソムリエ協会常務理事
定員:280名(満席)
テーマ:「テイスティングのコツ」
テイスティングは感覚的に表現するに留まってしまうと、かえって理解から遠ざかってしまいます。この色合いは、このフルーツの香りは、この酸味のタイプは、アフターフレーバーは、テイスティングにより感じられた特徴を分析、判断、理解へと繋げてゆく、論理的なテイスティングは、品揃え、サービス、ペアリング、楽しみ方へと広げてゆくことができます。
■森 覚(もり・さとる)ソムリエ
今回のセミナーの講師、森覚氏は第15回A.S.I.世界最優秀ソムリエコンクールの日本代表で出場、8位に入賞された方なので、業界では超有名人ですね。
<プロフィール>
http://www.conradtokyo.co.jp/news/detail/2749
しゃべりも面白くて、2時間あっという間で、とても良いセミナーでした。
■セミナーの構成
通常だと最初の1時間を講義、後半の1時間がテイスティング、ということが多いのですが、今回は8種類ブラインドでテイスティングするということで、もう最初からワインが注がれて、テイスティング開始です。
2杯を比較してテイスティングするという方法で、白ワインが2セット、赤ワインが2セットの、合計8種類。
全部飲んじゃうと酔っ払っうので、紙コップに吐き出すようにしないといけないのですが・・・美味しいとついつい飲んじゃうんですよね。
写真撮影および録音は、自分の勉強のためであればOKと、以前とくらべると大分寛容になってきました。
SNS等への投稿もOKですが、全国で同じワインでのセミナーを行うので、ワインのネタバラシはやめてくれとのことでした。
というわけで、今回はテイスティングのテクニックに関する内容だけまとめてみます。
■テイスティングの目的
目的をもってやらないと、ただ感想を述べるだけの飲み会になってしまう。
・分析し活用につなげる
・感覚を磨き、それを表現する力を身につける
※ちゃんと言葉にして表現できないとダメってことですね。
・欠点を探すのではなく長所を見つける
・主観(あくまで自分の感性)でコメントする
・先入観をもたない
※これ重要ですよね
■テイスティングのフォームをつくる
必ず自分の「フォーム」を作る。
「フォーム」とはコメントの順番や、判断の基点や軸などで、どんなワインがきても崩れないようにすることが重要。
とても甘いワインや、酸化しているワインなど、一部にすごく特徴のあるワインが来ても、外観→香り→味わい→アフターなどの順番は崩さないようにする。
■外観
森氏が推奨していたのは、ほぼ呼称資格試験の項目と同じ感じです。
・清澄度
・輝き
・色調
・濃淡
・ディスク、粘性
・泡立ち
■清澄について
意図して澱を残すなどしたワインは濁っている場合があるが、基本的にはクリアなワインが多い。
クリアなほど、醸造テクニックがしっかりしている証拠。
やはりワインは済んで輝きがあってキラキラしている方が良いと思う、という森ソムリエの意見でした。
■ワインの濃さの話
寒い地域は色づきが弱く、南の方は濃いというコメントは良く聞くけど、単純に南北で濃さが決まるわけではない。
樽の使用により色が濃くなったり、熟成により色が濃くなるケースがある。
甲州は香りを引き出すために色づきを犠牲にしている場合があるそうです。
■ルビーVSガーネット問題
根深い問題で、人により意見が違う。
(たしかにこれはテイスティングコメントの際の悩みどころでした)
意見が別れる事が多かったので、最近は「ダークチェリーレッド」「ラズベリーレッド」も選べるようになった。
でもこれも、どちらに分類するかは人によって意見が別れる可能性は消えていない。
■ロゼの色
ロゼの色を表現出来る人は少ない。
以下のような言い方がある。
ペタルドローズ
ラズベリーピンク
ピンクトパーズ、ピンクサファイア
サーモンピンク
オニオンスキン
アンバー、トパーズ
※どんな色かは調べてください
■香りを嗅ぐときのポイント
第1アロマ、第2アロマ、第3アロマの順番でコメントする。
樽香の印象が強くても最初に「樽」って言ってはダメ。
第1アロマ ブドウの品種の個性=フルーツ、スパイス、ハーブ、花、ミネラルなど。
第2アロマ 醗酵、製法に由来する香り。
第3アロマ 熟成に由来する香り。
第2アロマと第3アロマは共存しない。
最初はグラスを回さないで、第1アロマをとる。
そのときに香りが立たず、グラスを回して香りが立つ場合は還元状態である。
グラスを回しても香りが立たない場合は、閉じているという。
フルーツは「柑橘系・白系」「黄色系」「トロピカルフルーツ」の3つに大分類される。
3つが一緒に香りことはない。
白から黄色系、黄色系からトロピカルフルーツなどの範囲までで、白からトロピカルフルーツという組み合わせは無い。
(よくコメントでやってました、今後気をつけよう・・・)
■還元香
テニスボールの缶を開けたときのような、水道のホースのような香り。
■フローラル
黒っぽい色のワインは「スミレ」
若くて赤い色のワインは「バラ」のケースが多い
(これは逆かと思ってました・・・)
■酸味の話
「ph」※古い世代は「ペーハー」と読んでいたが、最近では「ピーエイチ」と言うらしい。
phが低いと酸が強い。
暖かいとブドウ自体がリンゴ酸を消費してしまうので、酸味が弱くなる、その場合MLF(マロラクティック発酵)はしない場合が多い。
寒い地域はリンゴ酸が多く残るので、MLFを行う。
その両方をブレンドして深みを出すような作り方もニューワールドでは進んでいる。
■甘みの話
「残糖の甘み」「果実味からくる甘み」「アルコールからくる甘み」の3つを分けて捉える。
「残糖の甘み」はシュガーの甘み、「アルコールからくる甘み」はラムやウォッカのような、強いアルコールで舌が麻痺することで感じる甘み。
■シンプルな料理とは
手間暇がかからない料理がシンプルといえる。
お刺身やカルパッチョ、素材を活かしたような料理。
手間暇かかるのは煮込んだり、ソースを作るようなもの。
シンプルなワインにはシンプルな料理、ボリュームのあるワインには手間暇かけた料理を合わせる。
■グラスサイズの選び方
私は、安いワイン=小さいグラス、良いワイン=大きいグラス、と簡単に考えていましたが、温度やアルコール度の強さも関係するそうです。
冷やして美味しいワインは小さいグラスで、少なく注いで、温度が上がらないうちに飲み終わるようにする。
アルコールの香りが強いものは大きなグラスで、鼻を遠ざけてアルコール香を下げる意味がある。
■樽のサイズ
最近は500リットルの「パンチョン」という樽のサイズがはやっている。
樽の影響は少なくてすむ。
■アメリカンオーク
ヴァニラにココナッツの印象がある。
■樽醗酵と樽熟成
樽醗酵→樽熟成よりも、ステンレス醗酵→樽熟成の方が樽の印象が残りやすい。
ステンレス醗酵の方がピュアなすっぴんな状態なので、樽の印象が残る。
樽醗酵は下地ができているので、樽熟成の時にそれほど香りが移らない。
■まとめ
日頃は自分なりでテイスティングしているので、ときどきこういうセミナーに出席して、コメントのブレなどを修正していく必要がありますね。
今年はなるべく多くのセミナーに出席したいと思います。
→過去のセミナー試飲会レポートはこちら
2016/12/31
ワインエキスパート二次試験用の資料(テイスティングシート)
<2017年8月22日>
2016年の二次試験結果発表では、選択項目までは開示されませんでした。
出題された品種のみですので、これはまた別途お知らせします。
どのような選択項目が出されたかは不明ですね~。
大きな変更は無いとは思いますが、最新の情報はワインスクールなどに行った方が良いかもしれません。
<2016年8月27日>
2015年度二次試験で使われたテイスティングシートのスマホ版を作ってみました。
いつでもどこでも二次試験の練習ができますね。
まあ、ワインバーのような照明が暗くて賑やかな場所でのテイスティングの練習は、なかなか難しいとは思いますが。
プリントして使いたい方は下のPDF版をお使いください。
・白ワイン・テイスティング用語選択用紙
・赤ワイン・テイスティング用語選択用紙
<2016年8月21日>
2015年の二次試験解答を反映してテイスティングシートをアップデートしました。
練習用テイスティングシート:解答編(PDFファイル)
最後に空のテイスティングシートがありますので、練習用にお使いください。
2015年にソムリエ協会が公開したテイスティングシートを元にしていますので、2016年の二次試験が同じ項目かどうかは分かりません。
ただ、過去問題の解答を見ていると、いろいろと方向性が見えてきますよね。
■関連情報(ワインエキスパート二次試験)
<2015年10月19日>
ソムリエ協会からテイスティングシートが公開されました。
いままで公開されなかった試験用のテイスティングシートですが、2015年のテイスティング銘柄発表の際に公表されましたね。
テイスティング用語選択用紙 2015年10月19日実施
みなさん、今後はこちらをお使いください。
------------------------------------------------------------------------
【注意!】
ここから下の内容は2015年以前の情報です。
2011年、2012年のテイスティングの解答をベースにして、テイスティングシートを作りました。
2012年にシニアワインエキスパートを受けましたが、試験前にこのシートを使って日頃から練習していたので、試験当日とってもスムーズに解答できました。
意味の分かりにくい項目がいくつかあるので、当日ぶっつけ本番だと、問の意味を理解するのに時間がかかってしまいますね。
<2015年7月20日>
26年度試験を反映して、テイスティングシートを改訂しました!
練習用テイスティングシート(PDFファイル)
23-26年度の解答項目は黒字、過去のテイスティングシートを参考に追加した項目は青字です。
香りの「豊かさ」が「第一印象」に変更になった以外は大項目の変更はありませんが、選択肢は少し見直しがあったようです。
解答項目は毎年見直しがあるようなので、今年の試験がこの項目で出るかどうかは分かりません。あくまで参考程度に考えてください。
<2015年7月26日>
平成26年度分のテイスティングシート解答編を追加しました!
練習用テイスティングシート:解答編(PDFファイル)
解答を黄色地でマークしています、他の品種の解答項目は黒字、過去のテイスティングシートを参考に追加した項目は青字です。
項目が複数選ばれていますが、選ばれている数が解答する数ではありません。解答のブレの範囲(正解の範囲)とご理解ください。
※同じ品種、生産国、生産年でも、ワインによって選択項目は変わってきますので、自宅テイスティングの解答として使う場合はあくまで参考と考えてください。
------------------------------------------------------------------------
【注意!】
ここから下の内容は2010年以前の情報です。
ワインエキスパートの二次試験に向けて、個人的に作った、テイスティングシートと過去問題のまとめ資料です。
【テイスティングシート】
練習用テイスティングシート(PDFファイル)

ベースはサントリースクールでもらったシートですが、認定試験の第19回から、第22回までの結果を追加していったので、項目数が多く、バラバラに入っている部分があります。
適当に、項目を消すなどして使ってください。
日頃からテイスティングの際に項目をチェックする練習をしておくと本番のときに慌てなくていいですね。
なにしろ意外と時間がありませんので、項目を選ぶのにあまり時間をかけていられないし、迷うと結構焦るんですよね。
迷わず、直感的にチェックを入れられる様に練習しておきましょう。
【過去問題の結果を反映したテイスティングシート】
テイスティングシート:過去問題結果(PDFファイル)

使い方としては、上記のテイスティングシートでテストした結果の正解の参考として使ってください。
シートの順番は開催順ではなく、品種毎にソートしてあります。
同じ品種でもテスト結果にばらつきがありますが、選択されやすい項目と、過去一度も選択されていない項目などありますので、とても参考になると思います。
【項目別にした過去問題結果の一覧】
ワイン認定試験過去問題結果一覧(PDFファイル)

このシートは本来のテイスティングの練習とは違いますが、テスト対策として参考になると思います。
品種によって、過去必ず選択されている項目や、意外と一度も選択された事が無い項目が一目瞭然で分かります。
グレーとブルーで色をつけてある項目は、19回以降一度も選ばれなかった項目で、特にブルーは通常のテイスティングで良く使うのに選ばれていない、ちょっと意外な項目です。
例を出すと、白ワインの香りの項目で「グレープフルーツ」「レモン」。
また「白い花」や「ミント」も今まで答えとして選択されていない項目です。
逆に今まで必ず入っている重要項目を記憶しておくと、テスト時間の節約になります。
■第23回のテスト結果から
選択項目は毎年変わっているようなので、上記シートの項目の中から必ず出る訳ではありません。
上記シートに無かった項目で、第23回の正解として出てきた項目は以下のようなものがあります。
【白:外観】
・スティル
・水様の粘性
・脚ができる粘性
【白:香り】
※新しい項目なし
【白:味わい】
※新しい項目なし
【赤:外観】
・脚ができる粘性
・トパーズ ※いままで項目としてはあったが、一度も選ばれた事がなかった
【赤:香り】
※新しい項目なし
【赤:味わい】
・心地よいアタック
・重量感のあるアタック
※今まで、心地よい渋みというのはありました
赤の香りの項目ですが、「カシス」と「ブラックチェリー」は相変わらず入っています。
第19回以降、赤ワインで選択されなかった事はないですね。
とりあえず入れておくといいのではないでしょうか。
「バランスのとれた」「現在飲み頃」も、いままで必ず入っている項目です。
その他、必ず入っている項目は覚えておく事をおすすめします。
※注意:第24回で、「現在飲み頃」が選ばれませんでした
■第24回のテスト結果から
シートに無い、正解の項目を調べてみました。
【白:外観】
・スティル
・澄みきった
・光沢のある
・澄んで艶のある
・淡い黄色
・脚ができる粘性
正解項目の表現が微妙に変わってきていますね。
また、いままで必ず入っていた「健全な」が正解項目から消えています。
当たり前だからかな?
【白:香り】
※新しい項目なし
いままで必ず入っていた、「ハーブ香」と「ミネラルのニュアンス」が外れました。
今回、甘口ワインが入ったからですね。
【白:味わい】
・甘口
・重厚な
甘口の白ワインが出ているので、その関連項目が新しく追加されてます。
(ソムリエ)オーストラリアのセミヨン、(ワインアドバイザー)イタリアのモスカート、(ワインエキスパート)ドイツのリースリングですね。
甘口のワインって日頃飲まないので難しそう。
ドイツのリースリングはともかく、オーストラリアのセミヨンって・・
「豊かな酸味」「バランスのとれた」「切れの良い後味」「現在飲み頃の」はいままで必ず入っている項目です。
【赤:外観】
・スティル
・澄みきった
・光沢のある
・脚ができる粘性
「健全な外観」が正解項目から消えてますね。
【赤:香り】
※微妙に表現が変わっているが新しい項目なし
ブラックチェリーとカシスは必ず入ってますね。鉄板です。
【赤:味わい】
・心地よいアタック
・重量感のあるアタック
・飲むには若すぎる
ついに、「現在飲み頃に入っている」神話が崩れましたね。
代わりに選ばれたのが、「飲むには若すぎる」。
ここの判断も難しそうですね。
「バランスのとれた」は不動で入っています。
2016年の二次試験結果発表では、選択項目までは開示されませんでした。
出題された品種のみですので、これはまた別途お知らせします。
どのような選択項目が出されたかは不明ですね~。
大きな変更は無いとは思いますが、最新の情報はワインスクールなどに行った方が良いかもしれません。
<2016年8月27日>
2015年度二次試験で使われたテイスティングシートのスマホ版を作ってみました。
いつでもどこでも二次試験の練習ができますね。
まあ、ワインバーのような照明が暗くて賑やかな場所でのテイスティングの練習は、なかなか難しいとは思いますが。
プリントして使いたい方は下のPDF版をお使いください。
・白ワイン・テイスティング用語選択用紙
・赤ワイン・テイスティング用語選択用紙
<2016年8月21日>
2015年の二次試験解答を反映してテイスティングシートをアップデートしました。
練習用テイスティングシート:解答編(PDFファイル)
最後に空のテイスティングシートがありますので、練習用にお使いください。
2015年にソムリエ協会が公開したテイスティングシートを元にしていますので、2016年の二次試験が同じ項目かどうかは分かりません。
ただ、過去問題の解答を見ていると、いろいろと方向性が見えてきますよね。
■関連情報(ワインエキスパート二次試験)
<2015年10月19日>
ソムリエ協会からテイスティングシートが公開されました。
いままで公開されなかった試験用のテイスティングシートですが、2015年のテイスティング銘柄発表の際に公表されましたね。
テイスティング用語選択用紙 2015年10月19日実施
みなさん、今後はこちらをお使いください。
------------------------------------------------------------------------
【注意!】
ここから下の内容は2015年以前の情報です。
2011年、2012年のテイスティングの解答をベースにして、テイスティングシートを作りました。
2012年にシニアワインエキスパートを受けましたが、試験前にこのシートを使って日頃から練習していたので、試験当日とってもスムーズに解答できました。
意味の分かりにくい項目がいくつかあるので、当日ぶっつけ本番だと、問の意味を理解するのに時間がかかってしまいますね。
<2015年7月20日>
26年度試験を反映して、テイスティングシートを改訂しました!
練習用テイスティングシート(PDFファイル)
23-26年度の解答項目は黒字、過去のテイスティングシートを参考に追加した項目は青字です。
香りの「豊かさ」が「第一印象」に変更になった以外は大項目の変更はありませんが、選択肢は少し見直しがあったようです。
解答項目は毎年見直しがあるようなので、今年の試験がこの項目で出るかどうかは分かりません。あくまで参考程度に考えてください。
<2015年7月26日>
平成26年度分のテイスティングシート解答編を追加しました!
練習用テイスティングシート:解答編(PDFファイル)
解答を黄色地でマークしています、他の品種の解答項目は黒字、過去のテイスティングシートを参考に追加した項目は青字です。
項目が複数選ばれていますが、選ばれている数が解答する数ではありません。解答のブレの範囲(正解の範囲)とご理解ください。
※同じ品種、生産国、生産年でも、ワインによって選択項目は変わってきますので、自宅テイスティングの解答として使う場合はあくまで参考と考えてください。
------------------------------------------------------------------------
【注意!】
ここから下の内容は2010年以前の情報です。
ワインエキスパートの二次試験に向けて、個人的に作った、テイスティングシートと過去問題のまとめ資料です。
【テイスティングシート】
練習用テイスティングシート(PDFファイル)

ベースはサントリースクールでもらったシートですが、認定試験の第19回から、第22回までの結果を追加していったので、項目数が多く、バラバラに入っている部分があります。
適当に、項目を消すなどして使ってください。
日頃からテイスティングの際に項目をチェックする練習をしておくと本番のときに慌てなくていいですね。
なにしろ意外と時間がありませんので、項目を選ぶのにあまり時間をかけていられないし、迷うと結構焦るんですよね。
迷わず、直感的にチェックを入れられる様に練習しておきましょう。
【過去問題の結果を反映したテイスティングシート】
テイスティングシート:過去問題結果(PDFファイル)

使い方としては、上記のテイスティングシートでテストした結果の正解の参考として使ってください。
シートの順番は開催順ではなく、品種毎にソートしてあります。
同じ品種でもテスト結果にばらつきがありますが、選択されやすい項目と、過去一度も選択されていない項目などありますので、とても参考になると思います。
【項目別にした過去問題結果の一覧】
ワイン認定試験過去問題結果一覧(PDFファイル)

このシートは本来のテイスティングの練習とは違いますが、テスト対策として参考になると思います。
品種によって、過去必ず選択されている項目や、意外と一度も選択された事が無い項目が一目瞭然で分かります。
グレーとブルーで色をつけてある項目は、19回以降一度も選ばれなかった項目で、特にブルーは通常のテイスティングで良く使うのに選ばれていない、ちょっと意外な項目です。
例を出すと、白ワインの香りの項目で「グレープフルーツ」「レモン」。
また「白い花」や「ミント」も今まで答えとして選択されていない項目です。
逆に今まで必ず入っている重要項目を記憶しておくと、テスト時間の節約になります。
■第23回のテスト結果から
選択項目は毎年変わっているようなので、上記シートの項目の中から必ず出る訳ではありません。
上記シートに無かった項目で、第23回の正解として出てきた項目は以下のようなものがあります。
【白:外観】
・スティル
・水様の粘性
・脚ができる粘性
【白:香り】
※新しい項目なし
【白:味わい】
※新しい項目なし
【赤:外観】
・脚ができる粘性
・トパーズ ※いままで項目としてはあったが、一度も選ばれた事がなかった
【赤:香り】
※新しい項目なし
【赤:味わい】
・心地よいアタック
・重量感のあるアタック
※今まで、心地よい渋みというのはありました
赤の香りの項目ですが、「カシス」と「ブラックチェリー」は相変わらず入っています。
第19回以降、赤ワインで選択されなかった事はないですね。
とりあえず入れておくといいのではないでしょうか。
「バランスのとれた」「現在飲み頃」も、いままで必ず入っている項目です。
その他、必ず入っている項目は覚えておく事をおすすめします。
※注意:第24回で、「現在飲み頃」が選ばれませんでした
■第24回のテスト結果から
シートに無い、正解の項目を調べてみました。
【白:外観】
・スティル
・澄みきった
・光沢のある
・澄んで艶のある
・淡い黄色
・脚ができる粘性
正解項目の表現が微妙に変わってきていますね。
また、いままで必ず入っていた「健全な」が正解項目から消えています。
当たり前だからかな?
【白:香り】
※新しい項目なし
いままで必ず入っていた、「ハーブ香」と「ミネラルのニュアンス」が外れました。
今回、甘口ワインが入ったからですね。
【白:味わい】
・甘口
・重厚な
甘口の白ワインが出ているので、その関連項目が新しく追加されてます。
(ソムリエ)オーストラリアのセミヨン、(ワインアドバイザー)イタリアのモスカート、(ワインエキスパート)ドイツのリースリングですね。
甘口のワインって日頃飲まないので難しそう。
ドイツのリースリングはともかく、オーストラリアのセミヨンって・・
「豊かな酸味」「バランスのとれた」「切れの良い後味」「現在飲み頃の」はいままで必ず入っている項目です。
【赤:外観】
・スティル
・澄みきった
・光沢のある
・脚ができる粘性
「健全な外観」が正解項目から消えてますね。
【赤:香り】
※微妙に表現が変わっているが新しい項目なし
ブラックチェリーとカシスは必ず入ってますね。鉄板です。
【赤:味わい】
・心地よいアタック
・重量感のあるアタック
・飲むには若すぎる
ついに、「現在飲み頃に入っている」神話が崩れましたね。
代わりに選ばれたのが、「飲むには若すぎる」。
ここの判断も難しそうですね。
「バランスのとれた」は不動で入っています。
ワインエキスパート試験の合格率
<2017年6月18日更新>
ソムリエ協会HPに掲載されていた合格率をグラフにしてみました。
ソムリエ、ワインアドバイザー(2016年からソムリエに統合)、ワインエキスパート

シニアソムリエ、シニアワインアドバイザー(2016年からシニアソムリエに統合)、シニアワインエキスパート

2016年からワインアドバイザーがソムリエに統合されましたが、その影響が合格率に出ていますね。
ワインアドバイザーは3つの区分の中では最も合格率が低かったのですが、統合されたことでソムリエの足を引っ張っているみたい。
それにしてもシニアソムリエの10.3%って・・・ 相当な難関ですよね~。
<以下2015年の記事>
いや~、シニアの資格は年々難しくなってきてますね。
私が受験した時は、一次試験しかありませんでしたが、今年は三次試験までありますからね。
試験対策も難しそうですが、みなさんの検討をお祈りします!
<以下2012年の過去記事 ※表はアップデートしてます>
ソムリエ協会HPに資格保有者・合格率が掲載されていましたので、表にしてみました。
試験内容にはそれほど差がないのに、ワインアドバイザーの合格率が極端に低いのは、会社やお店の指示で受験に行かされてて、モチベーションが低いのが原因??
いよいよ今週合格発表だと思いますが、一次試験合格していれば来年は筆記は無いので、しっかり1年かけてテイスティングの練習ができますよ。
ちなみに私はそのパターンでしたが、今となってはそれで良かったかなー、って思ってます。
ソムリエ協会HPに掲載されていた合格率をグラフにしてみました。
ソムリエ、ワインアドバイザー(2016年からソムリエに統合)、ワインエキスパート

シニアソムリエ、シニアワインアドバイザー(2016年からシニアソムリエに統合)、シニアワインエキスパート

2016年からワインアドバイザーがソムリエに統合されましたが、その影響が合格率に出ていますね。
ワインアドバイザーは3つの区分の中では最も合格率が低かったのですが、統合されたことでソムリエの足を引っ張っているみたい。
それにしてもシニアソムリエの10.3%って・・・ 相当な難関ですよね~。
<以下2015年の記事>
いや~、シニアの資格は年々難しくなってきてますね。
私が受験した時は、一次試験しかありませんでしたが、今年は三次試験までありますからね。
試験対策も難しそうですが、みなさんの検討をお祈りします!
<以下2012年の過去記事 ※表はアップデートしてます>
ソムリエ協会HPに資格保有者・合格率が掲載されていましたので、表にしてみました。
ソムリエ
|
ワインアドバイザー
|
ワインエキスパート
| |
2005
|
46.5%
|
34.4%
|
49.2%
|
2006
|
46.7%
|
28.7%
|
45.0%
|
2007
|
39.1%
|
22.4%
|
40.9%
|
2008
|
41.0%
|
22.1%
|
39.7%
|
2009
|
41.8%
|
22.2%
|
31.5%
|
2010
|
40.5%
|
24.5%
|
35.1%
|
2011
|
41.1%
|
23.3%
|
36.9%
|
2012
|
40.1%
|
24.7%
|
33.2%
|
2013
|
44.5%
|
26.7%
|
35.5%
|
2014
|
39.1%
|
30.4%
|
41.4%
|
2015
|
40.9%
|
24.6%
|
39.6%
|
2016
|
29.0%
|
―
|
38.2%
|
試験内容にはそれほど差がないのに、ワインアドバイザーの合格率が極端に低いのは、会社やお店の指示で受験に行かされてて、モチベーションが低いのが原因??
いよいよ今週合格発表だと思いますが、一次試験合格していれば来年は筆記は無いので、しっかり1年かけてテイスティングの練習ができますよ。
ちなみに私はそのパターンでしたが、今となってはそれで良かったかなー、って思ってます。
ワインエキスパート二次試験 過去の出題品種まとめ
ワインエキスパートのみですが、過去の二次試験で出た品種をまとめてみました。
■ワインエキスパート二次試験 過去に出題された白ワイン品種と生産国
<2017年8月24日追記>
ワインエキスパートはあまり範囲を広げずに、ベーシックな品種に絞っているように感じられますが、伝統産地とニューワールドの区別はしっかり把握しておく必要がありますね。
シャルドネについては、特に多くの産地をテイスティングしておくと良いでしょう。
<2016年8月21日追記>
平成27年度試験も前年同様にベーシック路線ですが、リースリングがオーストラリアというのがちょっと引っ掛けですね。
ヨーロッパとニューワールドのバランスを取っているのも前年同様です。
<2015年8月23日追記>
平成26年度試験はややベーシックに戻った感じがありますが、はじめてニュージーランドの「ソーヴィニヨン・ブラン」が出題されましたね。
傾向としてはヨーロッパとニューワールドとバランスを取って出題されているようです。
<2014年7月24日追記>
平成25年度試験で、いままで出ると言われ続けていた「甲州」が出題されました。
次に出るとしたらスペイン系の品種でしょうかね?
イタリア系の品種もやや気になるところです。
<2013年>
シャルドネ出題率は非常に高いですね。
従来は、フランスのシャルドネ、ドイツのリースリングが定番でしたが、最近はややひねってきてる傾向にあります。
ちなみに2012年のシニアワインエキスパート試験では、スペインのアルバリーニョが出題されました。
■ワインエキスパート二次試験 過去に出題された赤ワイン品種と生産国
<2017年8月24日追記>
オーストラリアは関税が低くなって売り場での面積が増えてきていて、スペインワインはすっかり定着していますが、出題品種はその年のワイン事情を反映していることが多いですね。
品種と産地の組み合わせはひねってないので、ベーシックな品種と産地の特徴をしっかり把握しておくことが重要ですね。
迷っても、主要品種の主要な産地から選択すれば良さそうです。
<2016年8月21日追記>
平成27年度試験は、白ワインと同様にベーシックな品種で、前年同様ですね。
カベルネ・ソーヴィニヨンがニューワールドで、シラーがヨーロッパという点がポイントでしょうか。
<2015年8月23日追記>
平成26年度試験は、白ワインと同様にベーシックな品種に戻った印象です。
いままでシラー(シラーズ)はオーストラリアのみでしたが、フランスに変わりました。
フランスのシラーってカベルネ・ソーヴィニヨンと迷うことが良くあるので、やや難しい品種だったのではないでしょうか。
<2014年8月22日追記>
赤ワインは、ここ5年間毎年新しい品種が出ていて、だいぶ出尽くした感がありますが、まだ大物が残ってましたね。
去年の白ワインで甲州が出題されましたが、赤ワインの日本品種はまだ出ていません。
そう「マスカット・ベーリーA」。
今年の要注目品種ではないでしょうか。
<2014年7月24日追記>
平成25年度試験で「カベルネ・フラン」が出題されましたね。
赤ワインは相変わらず予測不能状態です。
主要品種(カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、ピノ・ノワール、シラー)から1品種、その他から1品種というような出題になりそうですね。
<2013年6月20日追記>
24年度試験で出たのは、ガメイとネッビオーロ。
赤ワインはますます出題傾向が分からなくなってきてます。
何が出ても不思議じゃない感じですね。
ちなみにワインアドバイザー試験の方では、ジンファンデルが出題されました。
<2013年>
赤ワインはカベルネ・ソーヴィニヨンとシラーが定番で、以前はニューワールド比率が高い傾向にありましたが、ここ数年でヨーロッパが多く出題されました。
昨年はヨーロッパとニューワールドがそれぞれ出題されて、品種はベーシックなものに戻ってきましたね。
■ワインエキスパート二次試験 過去に出題されたリキュール
リキュールは範囲が広すぎて、まったく予想できません。
ちなみに2012年のシニアワインエキスパート試験では日本酒が出題され、特定名称、精米歩合、使用米、アルコール度、産地などが問われました。
ちなみに、ソムリエについては出題される品種が違いますのでご注意ください。
平成28年度試験では以下のような違いがあります。
<ソムリエ:平成28年度>
シャルドネ(フランス)、シラーズ(オーストラリア)、マスカット・ベーリーA(日本)、マディラ、バ・アルマニャック
■関連情報(ワインエキスパート二次試験)
<過去記事>
■2012年のソムリエ協会のテーマは「日本」
2013年3月に、世界最優秀ソムリエコンクールが日本で開催される事もあり、今年のソムリエ協会のテーマは、日本のワインと酒類です。
先日も横浜で、日本酒のテイスティングセミナーが開かれたばかりですね。
随分前から日本のワイン、特に甲州が出るのではと言われ続け、いまだに出たことはありませんが、今年あたりひょっとするかも??
<2014年7月24日追記>
平成25年度試験でついに甲州が出ましたね。
続けて出るのか分かりませんが、ひっかけでミュスカデあたりが出ると大混乱しそうですね。
■スペインに要注意
2012年のシニアワインエキスパート試験で出てビックリしたのが、アルバリーニョ。
市場でも、スペインワインの存在価値が大きくなっているので、今年も要注意ですね。
■ワインエキスパート二次試験 過去に出題された白ワイン品種と生産国
シャルドネ
|
リースリング
|
ムロン・ド・ ブルゴーニュ
|
ソーヴィニヨン・ ブラン
|
甲州
| |
16年度
|
フランス
| ||||
17年度
|
フランス
|
ドイツ
| |||
18年度
|
フランス
| ||||
19年度
|
日本
|
フランス
| |||
20年度
|
フランス
|
ドイツ
| |||
21年度
|
フランス
| ||||
22年度
|
日本
|
ドイツ
| |||
23年度
|
アメリカ
|
フランス
| |||
24年度
|
フランス
|
オーストラリア
| |||
25年度
|
フランス
|
日本
| |||
26年度
|
ドイツ
|
ニュージーランド
| |||
27年度
|
フランス
|
オーストラリア
| |||
28年度
|
アメリカ
|
フランス
| |||
シャルドネ
|
リースリング
|
ムロン・ド・ ブルゴーニュ
|
ソーヴィニヨン・ ブラン
|
甲州
|
<2017年8月24日追記>
ワインエキスパートはあまり範囲を広げずに、ベーシックな品種に絞っているように感じられますが、伝統産地とニューワールドの区別はしっかり把握しておく必要がありますね。
シャルドネについては、特に多くの産地をテイスティングしておくと良いでしょう。
<2016年8月21日追記>
平成27年度試験も前年同様にベーシック路線ですが、リースリングがオーストラリアというのがちょっと引っ掛けですね。
ヨーロッパとニューワールドのバランスを取っているのも前年同様です。
<2015年8月23日追記>
平成26年度試験はややベーシックに戻った感じがありますが、はじめてニュージーランドの「ソーヴィニヨン・ブラン」が出題されましたね。
傾向としてはヨーロッパとニューワールドとバランスを取って出題されているようです。
<2014年7月24日追記>
平成25年度試験で、いままで出ると言われ続けていた「甲州」が出題されました。
次に出るとしたらスペイン系の品種でしょうかね?
イタリア系の品種もやや気になるところです。
<2013年>
シャルドネ出題率は非常に高いですね。
従来は、フランスのシャルドネ、ドイツのリースリングが定番でしたが、最近はややひねってきてる傾向にあります。
ちなみに2012年のシニアワインエキスパート試験では、スペインのアルバリーニョが出題されました。
■ワインエキスパート二次試験 過去に出題された赤ワイン品種と生産国
カベルネ・ ソーヴィニヨン
|
シラー (シラーズ)
|
ピノ・ノワール
|
サンジョヴェーゼ
|
メルロー
|
テンプラニーリョ
|
ガメイ
|
ネッビオーロ
|
カベルネ・フラン
| |
16年度
|
アメリカ
|
オーストラリア
| |||||||
17年度
|
アメリカ
| ||||||||
18年度
|
オーストラリア
|
アメリカ
| |||||||
19年度
|
オーストラリア
| ||||||||
20年度
|
チリ
| ||||||||
21年度
|
イタリア
| ||||||||
22年度
|
フランス
| ||||||||
23年度
|
オーストラリア
|
スペイン
| |||||||
24年度
|
フランス
|
イタリア
| |||||||
25年度
|
アメリカ
|
フランス
| |||||||
26年度
|
フランス
|
アメリカ
| |||||||
27年度
|
アメリカ
|
フランス
| |||||||
28年度
|
オーストラリア
|
スペイン
| |||||||
カベルネ・ ソーヴィニヨン
|
シラー (シラーズ)
|
ピノ・ノワール
|
サンジョヴェーゼ
|
メルロー
|
テンプラニーリョ
|
ガメイ
|
ネッビオーロ
|
カベルネ・フラン
|
<2017年8月24日追記>
オーストラリアは関税が低くなって売り場での面積が増えてきていて、スペインワインはすっかり定着していますが、出題品種はその年のワイン事情を反映していることが多いですね。
品種と産地の組み合わせはひねってないので、ベーシックな品種と産地の特徴をしっかり把握しておくことが重要ですね。
迷っても、主要品種の主要な産地から選択すれば良さそうです。
<2016年8月21日追記>
平成27年度試験は、白ワインと同様にベーシックな品種で、前年同様ですね。
カベルネ・ソーヴィニヨンがニューワールドで、シラーがヨーロッパという点がポイントでしょうか。
<2015年8月23日追記>
平成26年度試験は、白ワインと同様にベーシックな品種に戻った印象です。
いままでシラー(シラーズ)はオーストラリアのみでしたが、フランスに変わりました。
フランスのシラーってカベルネ・ソーヴィニヨンと迷うことが良くあるので、やや難しい品種だったのではないでしょうか。
<2014年8月22日追記>
赤ワインは、ここ5年間毎年新しい品種が出ていて、だいぶ出尽くした感がありますが、まだ大物が残ってましたね。
去年の白ワインで甲州が出題されましたが、赤ワインの日本品種はまだ出ていません。
そう「マスカット・ベーリーA」。
今年の要注目品種ではないでしょうか。
<2014年7月24日追記>
平成25年度試験で「カベルネ・フラン」が出題されましたね。
赤ワインは相変わらず予測不能状態です。
主要品種(カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、ピノ・ノワール、シラー)から1品種、その他から1品種というような出題になりそうですね。
<2013年6月20日追記>
24年度試験で出たのは、ガメイとネッビオーロ。
赤ワインはますます出題傾向が分からなくなってきてます。
何が出ても不思議じゃない感じですね。
ちなみにワインアドバイザー試験の方では、ジンファンデルが出題されました。
<2013年>
赤ワインはカベルネ・ソーヴィニヨンとシラーが定番で、以前はニューワールド比率が高い傾向にありましたが、ここ数年でヨーロッパが多く出題されました。
昨年はヨーロッパとニューワールドがそれぞれ出題されて、品種はベーシックなものに戻ってきましたね。
■ワインエキスパート二次試験 過去に出題されたリキュール
リキュール
| ||
16年度
|
ルビー・ポート
| |
17年度
|
コニャック
| |
18年度
|
アルマニャック
| |
19年度
|
チェリーヒーリング
| |
20年度
|
泡盛
| |
21年度
|
アルマニャック
| |
22年度
|
アマレット
| |
23年度
|
ドライ・ヴェルモット
|
ウオッカ
|
24年度
|
ホワイト・キュラソーまたはコアントロー
|
カルヴァドス
|
25年度
|
カルヴァドス
|
トウニー・ポート
|
26年度
|
シングルモルト・ウイスキー
|
ガリアーノ
|
27年度
|
コニャック
|
アマレット
|
28年度
|
泡盛
| |
リキュールは範囲が広すぎて、まったく予想できません。
ちなみに2012年のシニアワインエキスパート試験では日本酒が出題され、特定名称、精米歩合、使用米、アルコール度、産地などが問われました。
ちなみに、ソムリエについては出題される品種が違いますのでご注意ください。
平成28年度試験では以下のような違いがあります。
<ソムリエ:平成28年度>
シャルドネ(フランス)、シラーズ(オーストラリア)、マスカット・ベーリーA(日本)、マディラ、バ・アルマニャック
■関連情報(ワインエキスパート二次試験)
<過去記事>
■2012年のソムリエ協会のテーマは「日本」
2013年3月に、世界最優秀ソムリエコンクールが日本で開催される事もあり、今年のソムリエ協会のテーマは、日本のワインと酒類です。
先日も横浜で、日本酒のテイスティングセミナーが開かれたばかりですね。
随分前から日本のワイン、特に甲州が出るのではと言われ続け、いまだに出たことはありませんが、今年あたりひょっとするかも??
<2014年7月24日追記>
平成25年度試験でついに甲州が出ましたね。
続けて出るのか分かりませんが、ひっかけでミュスカデあたりが出ると大混乱しそうですね。
■スペインに要注意
2012年のシニアワインエキスパート試験で出てビックリしたのが、アルバリーニョ。
市場でも、スペインワインの存在価値が大きくなっているので、今年も要注意ですね。
2015/07/12
第6回全日本J.S.A.ワインエキスパートコンクール予選を受けてきました
第6回全日本J.S.A.ワインエキスパートコンクール予選
■日時:2015年7月12日(日)
■会場:関東は京王プラザホテル
■出場資格:
(一社)日本ソムリエ協会 正会員でJ.S.A.ワインエキスパート有資格者
※ J.S.A.ワインエキスパート資格のみお持ちの方
■参加料:無料
■スケジュール:
12:10~ 受付
12:20~12:30 オリエンテーション
12:30~13:30 筆記試験
13:30~14:00 テイスティング
■公開決勝:2015年10月28日(水)高知県高知市
3年に一度行われる、ワインエキスパートコンクール。
今まではまったく関係のないイベントと思っていましたが、最近ワインの勉強をしてないので良い機会だと思って受験してきました。
結果は惨敗・・
清々しいほどの敗北感ですね、コテンパンにやられた感じです。
数えていませんでしたが、60~80問くらい出たのではないでしょうか。
すべて選択ではなく、記述式なので、うろ覚えの知識はまったく役にたちません。
昨年のワインエキスパート一次試験と同じ問題もいくつかあって予習はしてあったのですが、正確に記憶していなかったので答えることが出来ませんでした。
ちゃんと回答出来たのは10%くらいでしょうか・・・
半分くらいまでは無理やり埋めてみましたが、まったく自信がないですね~。
覚えてる問題はこんな感じ。
・ソムリエ協会の発足年と当時の正式名称
→みなさん、まずここは覚えましょう・・・
・マロラクティック醗酵の化学式を書きなさい
・90oeのエクスレ度を求めよ
・アルザス・グラン・クリュでシルヴァーナーが認められてるリューディ
→この問題、昨年のワインエキスパート一次試験で出たんですよね~。
・1615年に棚架け法を考案した人物
・パリティスティングの年と、その時の記者の名前
→「パリスの審判 カリフォルニア・ワインVSフランス・ワイン 」読んでたのに答えられなかった・・・
」読んでたのに答えられなかった・・・
・3月を過ぎると急に味が落ちて「猫またぎ」と言われる魚
などなど・・
心なしか、筆記試験が始まって最初の数分はペンを走らせる音がしなかったような・・・
みなさん、難問に当惑していたように感じました。
長い1時間の筆記試験が終わって、次は赤ワイン2つ白ワイン2つのブラインドティスティング。
それぞれ、ブドウ品種、生産国、アペラシオン、収穫年、アルコール度、を答えるのですが、最初の赤だけは自由記述があって感じた事を記載します。
1つ目の赤ワインは、ちょっと落ち着いた色調ながらまだ若い感じで、非常に香りの強いタイプでした。
ボルドー品種を使っているニューワールドワインって印象でしたが、味わいはやや大人しく、ちょっとまろやか過ぎる感じが日本のワインっぽかったので、品種はメルローで、日本の長野産と回答。
2つ目の赤ワインは、濃縮感のある果実感があって、ニューワールドっぽい残糖の多めのタイプだったので、ちょっと冒険してマルベックと回答。
国はアルゼンチン、産地はメンドーサにしておきました。
3つ目の白ワインは、ヨーロッパのローカル品種って印象で、何となくスペインっぽさを感じたので、アルバリーニョでスペイン、アペラシオンはよく分からないけど、カスティーリャ・イ・レオンと回答。
しかし、アルバリーニョってリアル・バイシャス原産なんですよね・・・ちょっと適当に答えすぎたか・・
4つ目の白ワインは、いかにもソーヴィニヨンブランって香り。あまり考えないでニュージーランドを選択しました。もちろんアペラシオンはマールボロ。
時間が余ったので、何度も飲み直したのですが、後から答えを変えると間違えるパターンが多いので、そのまま第一印象を大事にしておきました。
特に2つめの赤ワインは、シラーっぽくもあったので、ローヌや南仏の方が良かったかな~とちょっと後悔しています。
どちらも当たらないかもしれませんけど。
品種の発表は7月13日(月)、予選通過の発表は7月24日(金)。
まったく期待しないで、結果を待ちます。
それにしても、3年後にまた受験するかどうか・・・
相当勉強しないと難しいですね~。
ちなみに関東の会場、京王プラザホテル47階からは素敵な眺望を見ることができました。

<2015年7月13日追記>
テイスティングの答えが発表になりました。
【1】赤ワイン
主要ブドウ品種:テンプラニーリョ
生産国:スペイン
アペラシオン:リオハ
ブドウ収穫年:2009
アルコール度数:13.5%
【2】赤ワイン
主要ブドウ品種:マルベック
生産国:アルゼンチン
アペラシオン:メンドーサ
ブドウ収穫年:2012
アルコール度数:14.5%
【3】白ワイン
主要ブドウ品種:セミヨン
生産国:オーストラリア
アペラシオン:バロッサ・バレー
ブドウ収穫年:2012
アルコール度数:11.5%
【4】白ワイン
主要ブドウ品種:グリューナー・フェルトリーナー
生産国:オーストリア
アペラシオン:カンプタール
ブドウ収穫年:2013
アルコール度数:12.5%
筆記試験も難問の連続でしたが、ブラインドティスティングもかなり攻めた感じのラインナップ。
主要品種はしっかり外してありましたね。
冒険と思ったマルベックが意外と正解。
品種、国、アペラシオン、生産年を正解しました。
あとの3つはダメダメでしたね。
特に最初の赤ワインはテンプラニーリョだったんですね~。
スペインのワインは大樽でしっかり熟成してから出荷するので、生産年よりも若く感じる事がありますよね。
生産年も2012年くらいにしたような気がします。
この最初の赤ワインの回答が合否の鍵を握りそうですね。
というわけでテイスティングも撃沈でした・・・
気を引き締めてまた勉強のし直しです!
<2015年7月26日>
準決勝進出の12名が発表されましたね。
まあ、当たり前ですが私は入っていませんでした。。。
準決勝(非公開)・決勝(公開)は2015年10月28日(水)高知県高知市で開催とのことですが、もうちょっと近いと観に行きたいんですけどね~。
準決勝進出のみなさん、応援してます!
■日時:2015年7月12日(日)
■会場:関東は京王プラザホテル
■出場資格:
(一社)日本ソムリエ協会 正会員でJ.S.A.ワインエキスパート有資格者
※ J.S.A.ワインエキスパート資格のみお持ちの方
■参加料:無料
■スケジュール:
12:10~ 受付
12:20~12:30 オリエンテーション
12:30~13:30 筆記試験
13:30~14:00 テイスティング
■公開決勝:2015年10月28日(水)高知県高知市
3年に一度行われる、ワインエキスパートコンクール。
今まではまったく関係のないイベントと思っていましたが、最近ワインの勉強をしてないので良い機会だと思って受験してきました。
結果は惨敗・・
清々しいほどの敗北感ですね、コテンパンにやられた感じです。
数えていませんでしたが、60~80問くらい出たのではないでしょうか。
すべて選択ではなく、記述式なので、うろ覚えの知識はまったく役にたちません。
昨年のワインエキスパート一次試験と同じ問題もいくつかあって予習はしてあったのですが、正確に記憶していなかったので答えることが出来ませんでした。
ちゃんと回答出来たのは10%くらいでしょうか・・・
半分くらいまでは無理やり埋めてみましたが、まったく自信がないですね~。
覚えてる問題はこんな感じ。
・ソムリエ協会の発足年と当時の正式名称
→みなさん、まずここは覚えましょう・・・
・マロラクティック醗酵の化学式を書きなさい
・90oeのエクスレ度を求めよ
・アルザス・グラン・クリュでシルヴァーナーが認められてるリューディ
→この問題、昨年のワインエキスパート一次試験で出たんですよね~。
・1615年に棚架け法を考案した人物
・パリティスティングの年と、その時の記者の名前
→「パリスの審判 カリフォルニア・ワインVSフランス・ワイン
・3月を過ぎると急に味が落ちて「猫またぎ」と言われる魚
などなど・・
心なしか、筆記試験が始まって最初の数分はペンを走らせる音がしなかったような・・・
みなさん、難問に当惑していたように感じました。
長い1時間の筆記試験が終わって、次は赤ワイン2つ白ワイン2つのブラインドティスティング。
それぞれ、ブドウ品種、生産国、アペラシオン、収穫年、アルコール度、を答えるのですが、最初の赤だけは自由記述があって感じた事を記載します。
1つ目の赤ワインは、ちょっと落ち着いた色調ながらまだ若い感じで、非常に香りの強いタイプでした。
ボルドー品種を使っているニューワールドワインって印象でしたが、味わいはやや大人しく、ちょっとまろやか過ぎる感じが日本のワインっぽかったので、品種はメルローで、日本の長野産と回答。
2つ目の赤ワインは、濃縮感のある果実感があって、ニューワールドっぽい残糖の多めのタイプだったので、ちょっと冒険してマルベックと回答。
国はアルゼンチン、産地はメンドーサにしておきました。
3つ目の白ワインは、ヨーロッパのローカル品種って印象で、何となくスペインっぽさを感じたので、アルバリーニョでスペイン、アペラシオンはよく分からないけど、カスティーリャ・イ・レオンと回答。
しかし、アルバリーニョってリアル・バイシャス原産なんですよね・・・ちょっと適当に答えすぎたか・・
4つ目の白ワインは、いかにもソーヴィニヨンブランって香り。あまり考えないでニュージーランドを選択しました。もちろんアペラシオンはマールボロ。
時間が余ったので、何度も飲み直したのですが、後から答えを変えると間違えるパターンが多いので、そのまま第一印象を大事にしておきました。
特に2つめの赤ワインは、シラーっぽくもあったので、ローヌや南仏の方が良かったかな~とちょっと後悔しています。
どちらも当たらないかもしれませんけど。
品種の発表は7月13日(月)、予選通過の発表は7月24日(金)。
まったく期待しないで、結果を待ちます。
それにしても、3年後にまた受験するかどうか・・・
相当勉強しないと難しいですね~。
ちなみに関東の会場、京王プラザホテル47階からは素敵な眺望を見ることができました。

<2015年7月13日追記>
テイスティングの答えが発表になりました。
【1】赤ワイン
主要ブドウ品種:テンプラニーリョ
生産国:スペイン
アペラシオン:リオハ
ブドウ収穫年:2009
アルコール度数:13.5%
【2】赤ワイン
主要ブドウ品種:マルベック
生産国:アルゼンチン
アペラシオン:メンドーサ
ブドウ収穫年:2012
アルコール度数:14.5%
【3】白ワイン
主要ブドウ品種:セミヨン
生産国:オーストラリア
アペラシオン:バロッサ・バレー
ブドウ収穫年:2012
アルコール度数:11.5%
【4】白ワイン
主要ブドウ品種:グリューナー・フェルトリーナー
生産国:オーストリア
アペラシオン:カンプタール
ブドウ収穫年:2013
アルコール度数:12.5%
筆記試験も難問の連続でしたが、ブラインドティスティングもかなり攻めた感じのラインナップ。
主要品種はしっかり外してありましたね。
冒険と思ったマルベックが意外と正解。
品種、国、アペラシオン、生産年を正解しました。
あとの3つはダメダメでしたね。
特に最初の赤ワインはテンプラニーリョだったんですね~。
スペインのワインは大樽でしっかり熟成してから出荷するので、生産年よりも若く感じる事がありますよね。
生産年も2012年くらいにしたような気がします。
この最初の赤ワインの回答が合否の鍵を握りそうですね。
というわけでテイスティングも撃沈でした・・・
気を引き締めてまた勉強のし直しです!
<2015年7月26日>
準決勝進出の12名が発表されましたね。
まあ、当たり前ですが私は入っていませんでした。。。
準決勝(非公開)・決勝(公開)は2015年10月28日(水)高知県高知市で開催とのことですが、もうちょっと近いと観に行きたいんですけどね~。
準決勝進出のみなさん、応援してます!
2015/05/30
はじめてのワイン法 蛯原 健介 (著)
はじめてのワイン法
蛯原 健介 (著)
単行本: 367ページ
出版社: 虹有社 (2014/9/5)
発売日: 2014/9/5
商品パッケージの寸法: 18.8 x 13 x 2.6 cm
ワインエキスパート試験の中でも覚えるのが難しいワイン法ですが、この本は法律が制定されるまでの歴史や背景などが丁寧に書かれていて、とてもワイン法に興味を持たせてくれます。
ヨーロッパのワイン法は、昔から今の形で存在しているような印象がありますが、現在のワイン法になるまでには、暴動や流血、さまざまな利権関係などが影響していることが分かりますね。
どんだけ細かいんだよ、ってところまでワイン法で定められているのが、具体的な事例で紹介されています。
それに対して、日本のワイン法の不備と、その歴史的な背景、ワイン法が整備されていないことで世界に日本のワインが認めらなかった事なども丁寧に解説されています。
ただ現在は、山梨のワインをEU諸国に向けて本格的に輸出する段階になって法的障壁が明らかになり、甲州やマスカット・ベーリーAのOIV(国際ブドウ・ワイン機構)への登録、国税庁長官による地理的表示「山梨」の指定が行われ、対策が取られるようになりました。
日本のワイン法もその実現に一歩進みだしたと、筆者は語っています。
分厚い本(367ページ)なので一回読んでも10%も頭に入らないかもしれませんが、何度も読み直すとその都度新しい発見があるタイプの本ですね。
ワインエキスパートを受けようと思っている人にはおすすめの一冊です。
<本書のトピック>
ワイン法の最低限の事項は「ワインの定義」「原産地呼称」「ラベル表示のルール」。
近代以前のヨーロッパでは、ワインは水に替わる必需品で、重要な財産だったため法律の整備が必要だった。
古代エジプト時代に原産地呼称制度の原型があった。
パリ近郊にワイン産地が無いのは「20リユ規制」があったため。
19世紀以前の法規制は利権を守るための上からの規制、1860年代後半のフィロキセラ禍以降はワインの品質と産地表示の守るために変わった。
EUワイン法は、加盟国法に優位する。
AOP(保護原産地呼称ワイン)は、「原産地」の「呼称」を「保護」されたワイン。
IGP(保護地理的表示ワイン)は、「地理的表示」を「保護」されたワイン。
EUワイン法では適応される「ブドウ生産物」を17品目定めている。
1.ワイン 2.発酵中のワイン 3.ヴァン・ド・リクール 4.ヴァン・ムスー 5.優良ヴァン・ムスー 6.芳香性優良ヴァン・ムスー 7.炭酸ガス添加ヴァン・ムスー 8.ヴァン・ペテイアン 9.炭酸ガス添加ヴァン・ペテイアン 10.ブドウ果汁 11.部分醗酵ブドウ果汁 12.乾燥ブドウ由来の部分醗酵ブドウ果汁 13.濃縮ブドウ果汁 14.濃縮ブドウ調整果汁 15.乾燥ブドウ原料ワイン 16.過熟ブドウ原料ワイン 17.ワインビネガー
EUワイン法のワインとは「破砕された、もしくは破砕されていない新鮮なブドウ、またはブドウ果汁を部分的または完全にアルコール発酵させて生産されたもの」。
AOPワインは官能審査が義務、IGPワインは任意。
保護されるためには「生産基準書」の作成が必要。
ボルドーの格付の対象は醸造所、ブルゴーニュの格付の対象は原産地呼称と結びついている畑。
EUではショ糖による「補糖」が条件付きで認められている。
条件付きで「補酸」「除酸」も認められているが、「補糖」との併用は認められない。
「シャトー」「クロ」のラベル表示は、AOPに属するフランスのワインのみ表示可能。
EUワイン法は、特定の瓶の形状も使用条件を定めている。
近年EU産ワインの状況は厳しく思い切った減反政策を行ったが、ラングドック・ルーシヨンの減反希望が多く、ニューワールドとの競争で苦境にあることを示した。
減反で最も減ったブドウ品種は、「カリニャン」。
日本の酒税法ではワインは「果実酒」「甘味果実酒」に分類されるが、果実に含有される糖類の総量を超える補糖を行っても「甘味果実酒」として表示出来る。
大量の補糖はEUの基準に合わないため、輸出する場合は、EUワイン法の基準に適合していることを証明する必要がある。
国際的に認められていない水の添加や乾燥ブドウの使用も、日本の「果実酒」は認められている。
日本のワイナリーは農地法により農地の所有が規制されていたため「買いブドウ」を使用していたが、農地法改正により自社畑を持つことが出来るようになった。
「長野県原産地呼称管理制度」は長野の産地名は保護されていない、唯一「山梨」だけ「地理的表示」に指定され、保護される。
ワイン市場はグローバル化していて、国際基準に適合したワイン造りのルールが求められている。日本でもワイン法の整備は避ける事ができない。
2014/08/21
イーエックスワイン 品種別ハーフセット
ワインエキスパート2次試験対策は、基本の品種をブラインドで飲んでみるのが一番。
ハーフボトルのセットで、さらに模範解答までついているイーエックスワインさんのセットは2次試験対策にピッタリです。
基本の品種別ハーフ・6本セット 《情野ソムリエ模範解答付》 \9,800(税別)

品種別ワイン12本セット 《情野ソムリエ模範解答付》 \19,800(税別)

過去問題ワインセット 《JSA模範解答付》 \19,800(税別)

【注意】ワインの内容は常に変わっていますので、イーエックス・ワインさんのサイトでご確認ください。
セットは3タイプあります。
1)超基本のぶどう品種6本が入った、コンパクトなハーフセット
2)基本のぶどう品種12本が入ったベーシックなハーフセット
3)過去に出題されたワインタイプが12本入った、ハーフとフルボトルの混ざったセット
1) 「超基本」のぶどう品種6本をまとめた、コンパクトなハーフセット
<セット内容 ※すべてハーフボトル>
基本の白ワイン
◆ミュスカデ
ロワール/フランス
◆ソーヴィニヨン・ブラン
ロワール/フランス
◆シャルドネ
シャブリ/フランス
基本の赤ワイン
◆ピノ・ノワール
ブルゴーニュ/フランス
◆カベルネ・ソーヴィニヨン
ボルドー/フランス
◆シラー
ローヌ/フランス
もっとも良く出題される、基本品種6種類のハーフセット。
価格も9,800円とお手頃ですね。
基本の品種別ハーフ・6本セット 《情野ソムリエ模範解答付》 \9,800(税別)

ただ、最近の出題傾向としては、赤ワインがかなり幅広い範囲から出題されることもありますので、下記の12本セットの方がおすすめです。
2) 自由が丘ワインスクールが厳選した、基本ワイン12本を網羅するハーフワインセット
基本の赤ワイン
◆シラーズ/オーストラリア
◆カベルネ・フラン
ロワール/フランス
◆ガメイ
ブルゴーニュ/フランス
◆ピノ・ノワール
ブルゴーニュ/フランス
◆カベルネ・ソーヴィニヨン
ボルドー/フランス
◆シラー
ローヌ/フランス
基本の白ワイン
◆ミュスカデ
ローヌ/フランス
◆シャルドネ
ブルゴーニュ/フランス
◆リースリング
アルザス/フランス
◆ゲヴュルツトラミネール
アルザス/フランス
◆ソーヴィニヨン・ブラン
ロワール/フランス
◆シャルドネ
チリ
品種別ワイン10本セット 《情野ソムリエ模範解答付》 \19,800(税別)

基本品種を押さえたら、過去問題のワインもテイスティングしておくことも重要ですね。
以下のセットはソムリエ試験の方で出た過去問題ですが、エキスパートでも役に立つことは間違いありません。
3) 実際に出題されたワインを集めた、過去問題ワインセット
※同品種、同産地のワインをご用意しています。銘柄、ヴィンテージは実際に出題されたものとは異なります。
<セット内容 ☆マークはフルボトル>
過去出題の赤ワイン
◆カベルネ・ソーヴィニョン
チリ
◆グルナッシュ
ローヌ/フランス
◆メルロ
長野/日本☆
◆サンジョベーゼ
イタリア
◆テンプラニーリョ
スペイン
◆ジンファンデル
カリフォルニア/アメリカ
過去出題の白ワイン
◆ゲヴュルツトラミネール
アルザス/フランス
◆甲州
山梨/日本
◆リースリング
ドイツ
◆シャルドネ
長野/日本☆
◆ソーヴィニョン・ブラン
ニュージーランド☆
◆リースリング
オーストラリア☆
ワインセットとしても魅力的な内容ですね。
エキスパートはここ数年で、テンプラニーリョ、ガメイ、ネッビオーロ、カベルネ・フランが出ているので、幅広くワインを飲んでおく必要があります。
過去問題ワインセット 《JSA模範解答付》 \19,800(税別)

予算が許せば、3セットすべて欲しいところですが、ひとまず、2)の12本セットは抑えておいた方がいいかもしれません。
みなさんの健闘をお祈りします。
■関連情報(ワインエキスパート二次試験)
ハーフボトルのセットで、さらに模範解答までついているイーエックスワインさんのセットは2次試験対策にピッタリです。
基本の品種別ハーフ・6本セット 《情野ソムリエ模範解答付》 \9,800(税別)
品種別ワイン12本セット 《情野ソムリエ模範解答付》 \19,800(税別)
過去問題ワインセット 《JSA模範解答付》 \19,800(税別)
【注意】ワインの内容は常に変わっていますので、イーエックス・ワインさんのサイトでご確認ください。
セットは3タイプあります。
1)超基本のぶどう品種6本が入った、コンパクトなハーフセット
2)基本のぶどう品種12本が入ったベーシックなハーフセット
3)過去に出題されたワインタイプが12本入った、ハーフとフルボトルの混ざったセット
1) 「超基本」のぶどう品種6本をまとめた、コンパクトなハーフセット
<セット内容 ※すべてハーフボトル>
基本の白ワイン
◆ミュスカデ
ロワール/フランス
◆ソーヴィニヨン・ブラン
ロワール/フランス
◆シャルドネ
シャブリ/フランス
基本の赤ワイン
◆ピノ・ノワール
ブルゴーニュ/フランス
◆カベルネ・ソーヴィニヨン
ボルドー/フランス
◆シラー
ローヌ/フランス
もっとも良く出題される、基本品種6種類のハーフセット。
価格も9,800円とお手頃ですね。
基本の品種別ハーフ・6本セット 《情野ソムリエ模範解答付》 \9,800(税別)
ただ、最近の出題傾向としては、赤ワインがかなり幅広い範囲から出題されることもありますので、下記の12本セットの方がおすすめです。
2) 自由が丘ワインスクールが厳選した、基本ワイン12本を網羅するハーフワインセット
基本の赤ワイン
◆シラーズ/オーストラリア
◆カベルネ・フラン
ロワール/フランス
◆ガメイ
ブルゴーニュ/フランス
◆ピノ・ノワール
ブルゴーニュ/フランス
◆カベルネ・ソーヴィニヨン
ボルドー/フランス
◆シラー
ローヌ/フランス
基本の白ワイン
◆ミュスカデ
ローヌ/フランス
◆シャルドネ
ブルゴーニュ/フランス
◆リースリング
アルザス/フランス
◆ゲヴュルツトラミネール
アルザス/フランス
◆ソーヴィニヨン・ブラン
ロワール/フランス
◆シャルドネ
チリ
品種別ワイン10本セット 《情野ソムリエ模範解答付》 \19,800(税別)
基本品種を押さえたら、過去問題のワインもテイスティングしておくことも重要ですね。
以下のセットはソムリエ試験の方で出た過去問題ですが、エキスパートでも役に立つことは間違いありません。
3) 実際に出題されたワインを集めた、過去問題ワインセット
※同品種、同産地のワインをご用意しています。銘柄、ヴィンテージは実際に出題されたものとは異なります。
<セット内容 ☆マークはフルボトル>
過去出題の赤ワイン
◆カベルネ・ソーヴィニョン
チリ
◆グルナッシュ
ローヌ/フランス
◆メルロ
長野/日本☆
◆サンジョベーゼ
イタリア
◆テンプラニーリョ
スペイン
◆ジンファンデル
カリフォルニア/アメリカ
過去出題の白ワイン
◆ゲヴュルツトラミネール
アルザス/フランス
◆甲州
山梨/日本
◆リースリング
ドイツ
◆シャルドネ
長野/日本☆
◆ソーヴィニョン・ブラン
ニュージーランド☆
◆リースリング
オーストラリア☆
ワインセットとしても魅力的な内容ですね。
エキスパートはここ数年で、テンプラニーリョ、ガメイ、ネッビオーロ、カベルネ・フランが出ているので、幅広くワインを飲んでおく必要があります。
過去問題ワインセット 《JSA模範解答付》 \19,800(税別)
予算が許せば、3セットすべて欲しいところですが、ひとまず、2)の12本セットは抑えておいた方がいいかもしれません。
みなさんの健闘をお祈りします。
■関連情報(ワインエキスパート二次試験)
ワインエキスパート 呼称資格認定試験 二次試験対策講座
二次試験対策は、自宅での地道な練習も必要ですが、やはり試験対策セミナーで、実際の試験の雰囲気を味わってくる、というのも重要。
試験会場って、結構緊張しますからね~。
ざっと、各ワインスクールの2次試験対策講座を調べてみました。
※2014年8月9日更新しました。
■田崎真也ワインサロン
http://www.tasaki-shinya.com/winesalon/wine/jsa_taisaku.html
2次試験対策講座(テイスティング)
受講期間:1day
開講月:8月23日~9月15日
受講料:各回6,480円(税込)
白ワイン、赤ワイン、MIX、蒸留酒、実践1、実践2など、数パターンあります。
実際の試験の雰囲気を体験という点では、実践1、2あたりの受講がオススメでしょうか。
フリーは4320円なので、何回か入れると良いかもしれません。
■アカデミー・デュ・ヴァン
http://www.adv.gr.jp/cat/curriculum/tokyo/201404T/class/J-1404-16T.html
http://www.adv.gr.jp/cat/curriculum/tokyo/201404T/class/6805.html
受講期間:2014年8月19日(火)~ 9月15日(月)
受講料:一括 登録生 1コマ 5,400円 (税込) 一般・非登録生 1コマ 6,480円 (税込)
エキスパート対象は全20回!
コマ数が多すぎて、どれを選んでいいか分かりませんが、全部受けたら、129,600円!
本番形式が4回あるので、それを1~2回くらい受ければいいのではないでしょうか。
■Wine Salon EZ (ワインサロン・イーズィ)
http://www.wsez.jp/course/jsa2
◇二次デギュスタシオン対策講座[1回講座] ※全呼称対象
ワイン12種類
酒精強化ワイン、リキュールなど2種類
模範解答集付き
A. 白ワイン4種類
B. 赤ワイン4種類
C. Aから1種類(記憶のワイン)
+Bから1種類(記憶のワイン)
+白、赤ワイン各1本
+酒精強化ワイン又はワイン以外の酒2種類
・ワインはすべてブラインドでテイスティングをします。
・AとBのワインはテイスティング後に品種の特徴を解説します。
・Cのワインは本番と同様の試験形式で行います。
【受講料】
9,000円(税込)/1回
◇二次デギュスタシオン直前対策講座[1回講座]
ワイン16種類
酒精強化ワイン、リキュールなど全12種類〔各15cc 持ち帰り可〕
模範解答集付き
A. ワイン6種類(白ワイン3種類、赤ワイン3種類)
B. ワイン6種類(白ワイン3種類、赤ワイン3種類)
C. ワイン4種類 + 酒精強化ワイン、又はワイン以外の酒(白ワイン2種類、赤ワイン2種類、酒精強化ワイン、又はワイン以外の酒2種類)
D. 酒精強化ワイン、リキュール、F焼酎、ウイスキー、ブランデー、清酒、中国酒など(10種類)
・ワインはすべてブラインドでテイスティングをします。
・AとBのワインはテイスティング後に、品種の特徴を解説と品種を導き出すための方法を学びます。
・Cのワインは本番と同様の試験形式で行います。
・Dの酒精強化ワイン、又はワイン以外の酒は15cc持ち帰りができます。(容器は配布します)
・この講座で供出するワインは、毎回、国や銘柄、年号などが異なります。
【受講料】
16,000円(税込)/1回
ワインサロン・イーズィさんの2次試験対策講座はリーズナブルで実践的。
これは受けてみたくなりました。
■関連情報(ワインエキスパート二次試験)
試験会場って、結構緊張しますからね~。
ざっと、各ワインスクールの2次試験対策講座を調べてみました。
※2014年8月9日更新しました。
■田崎真也ワインサロン
http://www.tasaki-shinya.com/winesalon/wine/jsa_taisaku.html
2次試験対策講座(テイスティング)
受講期間:1day
開講月:8月23日~9月15日
受講料:各回6,480円(税込)
白ワイン、赤ワイン、MIX、蒸留酒、実践1、実践2など、数パターンあります。
実際の試験の雰囲気を体験という点では、実践1、2あたりの受講がオススメでしょうか。
フリーは4320円なので、何回か入れると良いかもしれません。
■アカデミー・デュ・ヴァン
http://www.adv.gr.jp/cat/curriculum/tokyo/201404T/class/J-1404-16T.html
http://www.adv.gr.jp/cat/curriculum/tokyo/201404T/class/6805.html
受講期間:2014年8月19日(火)~ 9月15日(月)
受講料:一括 登録生 1コマ 5,400円 (税込) 一般・非登録生 1コマ 6,480円 (税込)
エキスパート対象は全20回!
コマ数が多すぎて、どれを選んでいいか分かりませんが、全部受けたら、129,600円!
本番形式が4回あるので、それを1~2回くらい受ければいいのではないでしょうか。
■Wine Salon EZ (ワインサロン・イーズィ)
http://www.wsez.jp/course/jsa2
◇二次デギュスタシオン対策講座[1回講座] ※全呼称対象
ワイン12種類
酒精強化ワイン、リキュールなど2種類
模範解答集付き
A. 白ワイン4種類
B. 赤ワイン4種類
C. Aから1種類(記憶のワイン)
+Bから1種類(記憶のワイン)
+白、赤ワイン各1本
+酒精強化ワイン又はワイン以外の酒2種類
・ワインはすべてブラインドでテイスティングをします。
・AとBのワインはテイスティング後に品種の特徴を解説します。
・Cのワインは本番と同様の試験形式で行います。
【受講料】
9,000円(税込)/1回
◇二次デギュスタシオン直前対策講座[1回講座]
ワイン16種類
酒精強化ワイン、リキュールなど全12種類〔各15cc 持ち帰り可〕
模範解答集付き
A. ワイン6種類(白ワイン3種類、赤ワイン3種類)
B. ワイン6種類(白ワイン3種類、赤ワイン3種類)
C. ワイン4種類 + 酒精強化ワイン、又はワイン以外の酒(白ワイン2種類、赤ワイン2種類、酒精強化ワイン、又はワイン以外の酒2種類)
D. 酒精強化ワイン、リキュール、F焼酎、ウイスキー、ブランデー、清酒、中国酒など(10種類)
・ワインはすべてブラインドでテイスティングをします。
・AとBのワインはテイスティング後に、品種の特徴を解説と品種を導き出すための方法を学びます。
・Cのワインは本番と同様の試験形式で行います。
・Dの酒精強化ワイン、又はワイン以外の酒は15cc持ち帰りができます。(容器は配布します)
・この講座で供出するワインは、毎回、国や銘柄、年号などが異なります。
【受講料】
16,000円(税込)/1回
ワインサロン・イーズィさんの2次試験対策講座はリーズナブルで実践的。
これは受けてみたくなりました。
■関連情報(ワインエキスパート二次試験)
2014/08/17
誰でもできる手づくりワイン―仕込み2時間2か月で飲みごろ
誰でもできる手づくりワイン―仕込み2時間2か月で飲みごろ
永田 十蔵 (著)
単行本: 111ページ
出版社: 農山漁村文化協会 (2006/01)
発売日: 2006/01
商品パッケージの寸法: 20.8 x 14.8 x 1.4 cm
この本、まず最初に気になるのが酒税法。
すでに、この本のタイトルでアウトじゃないかと思いきや、アルコール度1%未満であればセーフみたいです。
ただ、この本には酒税法に関する項目はありません。
何となくきな臭い雰囲気の漂う本ですね。
気になるトピックスをまとめてみました
■カラー写真でワインの作り方がシンプルにまとめてある
ソムリエ協会の教本などにも掲載されているワイン造りのステップですが、手づくりだとさらに具体的で分かりやすいですね。
これからソムリエ協会の呼称資格試験を受験する人にも、とても参考になると思います。
■はしがきの内容
ワインつくりは単純で、ブドウをつぶして醗酵させ、果汁を搾って静置するだけで、2~3ヶ月で美味しいワインが完成する。
難しい知識は不要で人は少しの手助けをするだけで、自然の摂理でワインは出来る。
一般に流通しているワインは、添加物が入っているので、うまくない。
手作りワインと比べるとその差は歴然としている。
ワインつくりの極意は「何も足さない、何も引かない、余計なことはしない。」人が余計なことをしなければブドウの持つポテンシャルは最大に引き出されて最高のワインができる。
という内容ですが、流通や保存のことを考えなくて良い自家製のワインは、ナチュラルでワインの原点といえる味がするんでしょうね。
■白ワインでも果醪発酵
破砕した果皮・果肉をまるごと漬け込んで醗酵させるのは「果醪(かろう)醗酵」、果汁だけを醗酵させるのが「果汁醗酵」。
白ワインは通常、省スペースで醗酵タンクの効率が良いという経済的な理由で果汁醗酵をするが、白ブドウの果皮や果肉にも無色のポリフェノールや旨味成分が含まれているので、手作りワインは白ワインも果醪醗酵を勧める。
今後白ワインも果醪発酵する作り手が出てくるかもしれない、と指摘しています。
■一次発酵と二次発酵
一次発酵は開放した条件で、ある程度アルコールを生成して色素やタンニンなどの成分を溶出させるのが目的。長く続けると、雑菌が発生して醪の状態が悪くなり腐敗臭がつく、しかし短いと色素などが十分に出きらない。切り上げのタイミングは作り手のセンスによる。
二次発酵は酸化を防ぐために、エアーロック付きの密閉容器で酸素を遮断した状態で、糖が完全なアルコールに変わるまで行う。
■清澄・おり引き
ワインの見栄えを良くするために、工場での「清澄・おり引き」は、遠心分離器、珪藻土を使って濁り成分を濾過、ワインマスト酸化防止のために亜硫酸塩を添加、遠心分離器ではとれなかった微細な混濁物質をタンニン、ゼラチン、活性炭、ペクチダーぜなどを使っており引き、褐変防止にナイロン66などを添加することもある、そして最後の仕上げとして精密濾過機や火入れによって除菌、殺菌を行ったあとにボトリングをする。
手づくりワインはそのような真似をする必要はない、醗酵が終了しマストがクリアになったらおり引きをかねて新しい瓶に移す。
■ワインの熟成について
熟成したワインは、大量流通させる側のレトリックで、亜硫酸塩がほどほどに低減し飲みやすくなったことをありがたがるのではないか。ボトリング直後に亜硫酸塩を入れたものは飲めたシロモノではない。
手作りワインは熟成させるものではない、出来たてが最高の状態である。
■白ワインの醗酵について
白ワインで果醪発酵をする場合は、一次発酵は早めに切り上げる。
白ワインのマストは酸化されやすく、酸化防止剤を入れない限り褐変は避けられない。
手作りワインでは糖分を残すことが難しいので、スウィートタイプが飲みたい場合は、飲む直前に補糖する。使用する糖は砂糖よりも果糖(フルクトース)が良い。
■まとめ
ワインというのは基本的にシンプルなお酒なんだ、ということを気づかせてくれる本です。
何かとウンチクの多い飲み物ですが、ワインメーカーのマーケティングに消費者が踊らされている可能性も指摘しています。
どのような食材もそうですが、出来たてを現地で味わうのが最高の贅沢なんでしょうね。
いわゆるワインのウンチク本とはまったく違う角度からワインの造り方を理解出来ますので、ワイン資格試験を受ける人にはおすすめします。
ただし、本当にワインを造ってみるかどうかは、個人の判断にお任せします。
アルコール度1%未満であれば酒税法にはひっかからないみたいですので。
2012/09/25
平成24年度ワインエキスパート二次試験 出題品種
ワインエキスパート二次試験受けたみなさん、おつかれさまでした!
試験から開放されて、美味しいワイン飲んでますかー ゞ(≧∀≦。)ゞ
早速ソムリエ協会のホームページに出題品種が掲載されていました。
注:ワインアドバイザー・ワインエキスパート 供出No.5については、選択肢に不備があり、正解が2つになったようです。
鉄板のシャルドネは、ストレートにフランス。
それにひきかえ、リースリングがオーストラリア!
ここはちょっと迷ったのではないでしょうかね。
赤ワインは、特徴のあるガメイですが、試験となるとピノ・ノワールが出る確率が高いのでそちらを選んだ人も多いのでは・・
あとはまさかのネッビオーロですね。
スペイン押しかと思いきや、イタリアでくるあたり、一筋縄ではいきません。
わたし、毎年予想を外してますね、すみません・・
まあ、今年二次試験落ちても、来年は一次試験免除ですからねー。
試験から開放されて、美味しいワイン飲んでますかー ゞ(≧∀≦。)ゞ
早速ソムリエ協会のホームページに出題品種が掲載されていました。
ソムリエ
|
主なブドウ品種
|
国名
|
年号
|
1
|
リースリング
|
ドイツ
|
2009
|
2
|
ピノ・ノワール
|
アメリカ
|
2009
|
3
|
シラー
|
フランス
|
2008
|
4
|
ホワイトポート
| ||
5
|
ダーク・ラム
| ||
ワインアドバイザー
|
主なブドウ品種
|
国名
|
年号
|
1
|
ソーヴィニヨン・ブラン
|
ニュージーランド
|
2008
|
2
|
ガメイ
|
フランス
|
2009
|
3
|
ジンファンデル
|
アメリカ
|
2007
|
4
|
ジン
| ||
5
|
コアントロー 又は ホワイト・キュラソー
| ||
ワインエキスパート
|
主なブドウ品種
|
国名
|
年号
|
1
|
リースリング
|
オーストラリア
|
2010
|
2
|
シャルドネ
|
フランス
|
2011
|
3
|
ガメイ
|
フランス
|
2009
|
4
|
ネッビオーロ
|
イタリア
|
2007
|
5
|
コアントロー 又は ホワイト・キュラソー
| ||
6
|
カルヴァドス
| ||
鉄板のシャルドネは、ストレートにフランス。
それにひきかえ、リースリングがオーストラリア!
ここはちょっと迷ったのではないでしょうかね。
赤ワインは、特徴のあるガメイですが、試験となるとピノ・ノワールが出る確率が高いのでそちらを選んだ人も多いのでは・・
あとはまさかのネッビオーロですね。
スペイン押しかと思いきや、イタリアでくるあたり、一筋縄ではいきません。
わたし、毎年予想を外してますね、すみません・・
まあ、今年二次試験落ちても、来年は一次試験免除ですからねー。
2012/09/03
日本酒の基礎から学ぶテイスティングセミナー 日本ソムリエ協会関東支部 第4回例会セミナー
日本ソムリエ協会関東支部の第4回例会セミナー「日本酒の基礎から学ぶテイスティングセミナー」に参加してきました。
【開催日時】
平成24年9月3日(月)14:00~16:00
【会場】
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 4階 宴会場「清流」
【講師】
宮坂 直孝 氏
宮坂醸造(株) 代表取締役社長
今年のソムリエ協会は、日本のワインや酒類を見直す、というテーマで活動をしているそうです。
来年3月に、日本で世界ソムリエ選手権があり、世界のトップソムリエやワイン関係者が日本に大勢来るので、その時に日本のワインや酒類をきちんとアピール出来るように、という理由があるようですね。
■真澄とは?
長野県諏訪市にある創業350年の蔵元、宮坂醸造株式会社のメインブランドの清酒が「真澄」です。
吟醸酒用および普通醸造用に適する「協会7号」酵母の発祥の蔵であり、協会7号酵母は全国の70%の清酒メーカーで使われています。
海外展開も積極的に行い、世界最大の酒の見本市「Vinexpo(ヴィネクスポ)」などにも出展しています。
■海外で人気のある日本酒
真澄の出荷比率は、北米が30%、アジアが40%、ヨーロッパが15%。
ただ売るのではなく、海外のパートナーと組んで、レストランなどで、日本酒のセミナーを行い、啓蒙活動を続けているいます。
日本酒の製造工程は複雑なので、簡単に5ステップで説明し、必ずテイスティングを行います。
日本酒はデリケートなので、海外で品質を守るのが難しく、管理出来ないスーパーなどには売らないそうです。
これからは伸びるのはアジア、ヨーロッパは売り上げは少ないが、質を問われる重要な市場と考えています。
■日本酒とワインの造り方の違い
果実ベースの醸造酒は果汁の糖分をアルコールにすればいいが、穀類ベースの醸造酒はデンプンを糖分に変えてから、アルコールにするステップがあります。
特に日本酒は、糖化を醗酵が同時に進行するのが特徴です。
■複雑で分かりにくい日本酒の分類
純米酒、大吟醸、生酒、いろいろあって分かりにくい日本酒の分類ですが、基本は4つの分類基準です。
<原材料>
アルコールを添加しない:純米酒
アルコールを添加する:本醸造、アルコール添加酒
<精米歩合>
49%以下:大吟醸酒
50~59%:吟醸酒
60%以上:普通種
<加熱処理>
加熱処理を全くしない:生酒
加熱処理1回:生詰酒、生貯蔵酒
加熱処理2回:その他
<加水>
加水(割り水)しない:原酒
加水(割り水)する:その他
■お米を削るわけ
お米のタンパク質や脂質を取り除き、純粋なデンプン質だけにする意味があるようです。
■テイスティング
(1)みやさか やわらか純米 55
分類:純米
米の品種:美山錦、山田錦
精米歩合:55%
酵母:9号系、7号系
アルコール分:12度
日本酒度:-5前後
酸度:1.3前後
アミノ酸度:1.0前後
アルコール度12度の日本酒。
ランチではほとんど日本酒は飲まれなくなり、ワイン程度にアルコール度が低いものを造って欲しいという要望から生まれた。
飲食店で人気があり、これから主流になるかもしれない。
ただ水で薄めればいいというものではなく、原酒の段階でバランスをとるために工夫している。
(2)真澄 純米吟醸 辛口生一本
分類:純米吟醸
米の品種:美山錦、山田錦
精米歩合:55%
酵母:9号系
アルコール分:15度
日本酒度:+6前後
酸度:1.3前後
アミノ酸度:1.0前後
真澄で一番売れている辛口。
日本酒の基礎をしっかり抑えている。
フルーティさや甘みが無く、辛口。
毎年工夫して改善していて、この日本酒が真澄の評価になる。
(3)真澄 純米大吟醸 七號
分類:純米大吟醸
米の品種:美山錦
精米歩合:45%
酵母:7号系
アルコール分:16度
日本酒度:-1前後
酸度:1.7前後
アミノ酸度:1.3前後
山廃仕込みで7號酵母を使い、米は山田錦ではなく、長野産の美山錦を使っている。
真澄らしさやテロワールを意識している。
フワラリィ(フローラル)の香りを強く出す酵母があるが、この日本酒は違い、穏やかな印象。
酸がキレイなため、ヨーロッパでも人気がある。
日本酒を飲んでないソムリエも酸をブリッジで入っていけるためである。
あまり香りが強い大吟醸は食事には合わせにくい。
山廃仕込みは、味に深みと酸が出るのが特徴。
<山廃とは>
酒母の温度を上げたり下げたりして、雑菌の繁殖をふせぐ。
熱湯を入れた木樽を酒母に入れてかき混ぜる、一定の温度になると取り出す。
ノコギリの歯のような温度変化。
今は醸造用の乳酸を入れて雑菌の繁殖を防ぐが、昔はこの方法で乳酸を発生させていた。
温度変化の間に、いろいろな酒母の中でいろいろな菌が戦い、味に深みが出る。
(4)純米吟醸 浦霞 禅
分類:純米吟醸
米の品種:トヨニシキ、山田錦
精米歩合:50%
酵母:自家酵母
アルコール分:15度以上16度未満
日本酒度:+1.0~+2.0
酸度:1.3
アミノ酸度:1.2
やわらかい米の味。
特異な香りは無く、スタンダードで、お刺身が美味しくなりそうなタイプ。
後味は辛く、日本酒らしい味わい。
(5)月の桂 大極上 中汲 にごり酒
分類:純米酒(活性にごり酒)
米の品種:五百万石
精米歩合:55%
酵母:協会901
アルコール分:17.2%
日本酒度:+3
酸度:1.7
アミノ酸度:1.4
にごり酒は、特徴がはっきりしているので海外で人気がある。
実際にはもう少し甘いものが人気。
にごり酒は専用の瓶詰めラインが必要で管理も大変。
小規模の清酒メーカーではなかなか難しい。
■感想
一時期、ワインのようなフルーティな日本酒が話題になったことがありましたが、結局主流にはなりませんでしたね。
今回特に、日本酒には日本酒らしい香りがあると再認識しました。
爽やかさがあって、それはフルーツではなく、清々しい大気の香りとでもいうか、自然をイメージさせる香りなんですよね。
アルコール度12度の日本酒は、これはあり、と思いました。
しっかりした日本酒と飲み比べると頼りない感じですが、普通の家庭の食事に合わせるなら、これくらいがちょうどいいのではないでしょうか。
10度を下回るとバランスをとるのが大変だ、と言っていたが、確かに12度で軽さの限界のような印象です。
一番美味しかったのは、真澄 純米大吟醸 七號。
とても香りが良くて、味わいも酸がキリッとしまった印象で、キレイな空気感を持っている日本酒でした。
日本酒の文化を守り、世界に発信していくアイデアとアクションを持っている社長と、有能な海外担当で、「真澄」はこれからもどんどん伸びるでしょうね。
こういう熱意のある日本酒メーカーが伝統文化を守ってくれているのはとても心強く感じました。
私もワインばっかりじゃなくて、日本酒も飲むようにしよう・・
【開催日時】
平成24年9月3日(月)14:00~16:00
【会場】
横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ 4階 宴会場「清流」
【講師】
宮坂 直孝 氏
宮坂醸造(株) 代表取締役社長
今年のソムリエ協会は、日本のワインや酒類を見直す、というテーマで活動をしているそうです。
来年3月に、日本で世界ソムリエ選手権があり、世界のトップソムリエやワイン関係者が日本に大勢来るので、その時に日本のワインや酒類をきちんとアピール出来るように、という理由があるようですね。
■真澄とは?
長野県諏訪市にある創業350年の蔵元、宮坂醸造株式会社のメインブランドの清酒が「真澄」です。
吟醸酒用および普通醸造用に適する「協会7号」酵母の発祥の蔵であり、協会7号酵母は全国の70%の清酒メーカーで使われています。
海外展開も積極的に行い、世界最大の酒の見本市「Vinexpo(ヴィネクスポ)」などにも出展しています。
■海外で人気のある日本酒
真澄の出荷比率は、北米が30%、アジアが40%、ヨーロッパが15%。
ただ売るのではなく、海外のパートナーと組んで、レストランなどで、日本酒のセミナーを行い、啓蒙活動を続けているいます。
日本酒の製造工程は複雑なので、簡単に5ステップで説明し、必ずテイスティングを行います。
日本酒はデリケートなので、海外で品質を守るのが難しく、管理出来ないスーパーなどには売らないそうです。
これからは伸びるのはアジア、ヨーロッパは売り上げは少ないが、質を問われる重要な市場と考えています。
■日本酒とワインの造り方の違い
果実ベースの醸造酒は果汁の糖分をアルコールにすればいいが、穀類ベースの醸造酒はデンプンを糖分に変えてから、アルコールにするステップがあります。
特に日本酒は、糖化を醗酵が同時に進行するのが特徴です。
■複雑で分かりにくい日本酒の分類
純米酒、大吟醸、生酒、いろいろあって分かりにくい日本酒の分類ですが、基本は4つの分類基準です。
<原材料>
アルコールを添加しない:純米酒
アルコールを添加する:本醸造、アルコール添加酒
<精米歩合>
49%以下:大吟醸酒
50~59%:吟醸酒
60%以上:普通種
<加熱処理>
加熱処理を全くしない:生酒
加熱処理1回:生詰酒、生貯蔵酒
加熱処理2回:その他
<加水>
加水(割り水)しない:原酒
加水(割り水)する:その他
■お米を削るわけ
お米のタンパク質や脂質を取り除き、純粋なデンプン質だけにする意味があるようです。
■テイスティング
(1)みやさか やわらか純米 55
分類:純米
米の品種:美山錦、山田錦
精米歩合:55%
酵母:9号系、7号系
アルコール分:12度
日本酒度:-5前後
酸度:1.3前後
アミノ酸度:1.0前後
アルコール度12度の日本酒。
ランチではほとんど日本酒は飲まれなくなり、ワイン程度にアルコール度が低いものを造って欲しいという要望から生まれた。
飲食店で人気があり、これから主流になるかもしれない。
ただ水で薄めればいいというものではなく、原酒の段階でバランスをとるために工夫している。
(2)真澄 純米吟醸 辛口生一本
分類:純米吟醸
米の品種:美山錦、山田錦
精米歩合:55%
酵母:9号系
アルコール分:15度
日本酒度:+6前後
酸度:1.3前後
アミノ酸度:1.0前後
真澄で一番売れている辛口。
日本酒の基礎をしっかり抑えている。
フルーティさや甘みが無く、辛口。
毎年工夫して改善していて、この日本酒が真澄の評価になる。
(3)真澄 純米大吟醸 七號
分類:純米大吟醸
米の品種:美山錦
精米歩合:45%
酵母:7号系
アルコール分:16度
日本酒度:-1前後
酸度:1.7前後
アミノ酸度:1.3前後
山廃仕込みで7號酵母を使い、米は山田錦ではなく、長野産の美山錦を使っている。
真澄らしさやテロワールを意識している。
フワラリィ(フローラル)の香りを強く出す酵母があるが、この日本酒は違い、穏やかな印象。
酸がキレイなため、ヨーロッパでも人気がある。
日本酒を飲んでないソムリエも酸をブリッジで入っていけるためである。
あまり香りが強い大吟醸は食事には合わせにくい。
山廃仕込みは、味に深みと酸が出るのが特徴。
<山廃とは>
酒母の温度を上げたり下げたりして、雑菌の繁殖をふせぐ。
熱湯を入れた木樽を酒母に入れてかき混ぜる、一定の温度になると取り出す。
ノコギリの歯のような温度変化。
今は醸造用の乳酸を入れて雑菌の繁殖を防ぐが、昔はこの方法で乳酸を発生させていた。
温度変化の間に、いろいろな酒母の中でいろいろな菌が戦い、味に深みが出る。
(4)純米吟醸 浦霞 禅
分類:純米吟醸
米の品種:トヨニシキ、山田錦
精米歩合:50%
酵母:自家酵母
アルコール分:15度以上16度未満
日本酒度:+1.0~+2.0
酸度:1.3
アミノ酸度:1.2
やわらかい米の味。
特異な香りは無く、スタンダードで、お刺身が美味しくなりそうなタイプ。
後味は辛く、日本酒らしい味わい。
(5)月の桂 大極上 中汲 にごり酒
分類:純米酒(活性にごり酒)
米の品種:五百万石
精米歩合:55%
酵母:協会901
アルコール分:17.2%
日本酒度:+3
酸度:1.7
アミノ酸度:1.4
にごり酒は、特徴がはっきりしているので海外で人気がある。
実際にはもう少し甘いものが人気。
にごり酒は専用の瓶詰めラインが必要で管理も大変。
小規模の清酒メーカーではなかなか難しい。
■感想
一時期、ワインのようなフルーティな日本酒が話題になったことがありましたが、結局主流にはなりませんでしたね。
今回特に、日本酒には日本酒らしい香りがあると再認識しました。
爽やかさがあって、それはフルーツではなく、清々しい大気の香りとでもいうか、自然をイメージさせる香りなんですよね。
アルコール度12度の日本酒は、これはあり、と思いました。
しっかりした日本酒と飲み比べると頼りない感じですが、普通の家庭の食事に合わせるなら、これくらいがちょうどいいのではないでしょうか。
10度を下回るとバランスをとるのが大変だ、と言っていたが、確かに12度で軽さの限界のような印象です。
一番美味しかったのは、真澄 純米大吟醸 七號。
とても香りが良くて、味わいも酸がキリッとしまった印象で、キレイな空気感を持っている日本酒でした。
日本酒の文化を守り、世界に発信していくアイデアとアクションを持っている社長と、有能な海外担当で、「真澄」はこれからもどんどん伸びるでしょうね。
こういう熱意のある日本酒メーカーが伝統文化を守ってくれているのはとても心強く感じました。
私もワインばっかりじゃなくて、日本酒も飲むようにしよう・・
2012/09/02
自宅でのブラインドテイスティング練習方法
(1)お手伝いしてくれる人にワインを開けてもらいます。
人に手伝ってもらい、数種類のワインを開けます。イーエックスワイン 品種別ハーフセット 12本だったら、赤か白、6本いっぺんに開けてしまいましょう!
日頃そんな贅沢は出来ませんからね~。
試験勉強の機会を利用して、いろいろなワインをいっぺんに楽しみましょう!
(2)ボトルとグラスに目印のシールを貼っておきましょう。
どのグラスがどのワインだったか分からなくなったら、せっかくのテイスティング練習の意味が無くなってしまいます。
事前にシールなどを準備して、お手伝いの人にボトルとワイングラスに貼ってもらいましょう。
(3)グラスを紙の筒などで目隠ししましょう。
6つ並んでいると、外観の比較などで最初に当たりをつけてしまいます。
すべて外観を隠しておいて、一種類づつ、順番にテストすることをオススメします。
(4)いよいよテイスティング
一つづつ順番にテイスティングしていきましょう。
紙の筒を1つづつ取って、外観、香り、味わい、品種や生産国などをチェックしていきましょう。
事前にテイスティングシートをワインの本数準備しておき、1本あたり5分くらいを目安に、スピーディに解答していく練習をしましょう。
(5)前のワインが間違ってた、と思っても後戻りしない
順番にテイスティングしていくと、あれ、こっちがシラーだった?みたいな事が普通にあります。
その際でも後戻りせずに、しっかり今感じている項目をチェックしていきましょう。
すべてワインのテイスティング終わってから、ネタばらしと答え合わせをしましょう。
自宅でのテイスティングの間違いはとても勉強になります。今までイメージしていた品種の特徴が、ブラインドだと全然違ってる、なんてこともよくあります。
しっかり自分のクセも把握していくことが重要ですね。
模範解答と自分の解答を付きあわせてみて、外れている項目については、もう一度テイスティングして確認しておきましょう。
(6)テストが終わったら、お手伝いしてくれた人にごちそうしましょう。
ハーフボトル6本だとフルボトルで3本分。
とても1人では飲みきれないので、手伝ってくれた人やお友達に、パーっとワインをごちそうしましょう。
「このワインどう思う?」って人の感想を聞くのもとても参考になりますね。
■関連情報(ワインエキスパート二次試験)
■楽天ショップへのリンク
INAO(イナオ) テイスティンググラス 6客セット
2012/08/12
日本ソムリエ協会 平成24年度 ワインエキスパート 呼称資格認定試験
ワインエキスパート呼称資格認定試験 一次試験が近づいてきました。
分厚い教本を読み込んでの、最後の追い込みに入っている事かと思います。
少しでも役に立ちそうな情報をまとめてみました。
右の写真はシニアワインエキスパートのバッジですが、デザインは同じみたい。
このバッジが届いたときは感無量です。みんながんばれ! p( ̄0 ̄)/
■教本は一通り目を通すべし!
試験内容は、教本の内容がそのまま出るパターンが多いので、分厚い本ですが、一通り目を通しておく必要があります。
ただ、それではポイントが分かりにくいので、参考書も別に購入してポイントを重点的に覚える事も必要ですね。
<参考書例>
◇ワイン受験講座 2012
私の受験時(2005年版)はA5サイズで持ち運びやすく、会社の行き帰りにずっと勉強してましたが、今はB5サイズでちょっと大きめですね。
A5サイズだと以下のテキストもあります。
◇改訂新版 30日間ワイン完全マスター2012 (Winart Book)
この参考書は、コンパクトに良くまとまっていて、分かりやすいですね。 (⌒_⌒)
残り少ない休日はじっくりと教本を読み込んで、平日は参考書を持ち歩いてどこでも勉強、というパターンはいかがでしょう。
■過去問題は必ずやること! ( ̄‥ ̄)/
過去問題が出る確率はかなり高いので、必ずやっておく必要があります。
日本ソムリエ協会の会員になると、ホームページで過去問題のPDFをダウンロードできるので、オススメです。
http://www.sommelier.jp/
入会金・初年度年会費は25,000円ですが、8月入会だと月割で安くなって、16,250円。
来年以降の年会費は15,000円です。(値上げしなければね)
ちなみに、会員は合格発表をホームページで確認できますね。
ワインセミナーなどにも参加出来て、情報ぎっしりの機関紙も隔月で届きます。
その他にも、過去の試験問題をまとめた本もあります。
◇改訂新版 ワインの過去問400 ソムリエ、ワインアドバイザー、ワインエキスパート呼称資格認定試験過去問題と解説でワインを学ぶ (Winart Book)
◇田辺由美のワインノート〈2012年版〉ソムリエ、ワインアドバイザー、ワインエキスパート認定試験合格のための問題と解説
「田辺由美のワインノート」はワイン呼称資格認定試験ではバイブル的な存在ですね。
私も買いましたが、あまりに問題数が多くて、全部は出来ませんでした・・・
( ̄∇ ̄*)ゞエヘヘ
■短期間で頭にたたきこむ!
ワインエキスパート試験は、とにかく記憶するものが多くて大変。
さまざまな方法でアクションしながら覚える事も重要ですね。
私の場合、どうしても覚えにくいものは単語帳を使って、常に持ち運んで見ていました。
自分で書き込む、というアクションも記憶につながります。
こういった本もあるんですよね、私は使いませんでしたが。
◇ワイン受験ゴロ合わせ暗記法〈2011〉
「ムートンは一級並(1973年)と言われていた天才(ピカソ)。」
シャトー・ムートン・ロートシルトが1級に格上げされた年とそのラベルの画家ですね。
なるほど、これは覚えるかも。 ( ̄∧ ̄)ふむふむ
試験はもう目前、あとはやるしかありません。
みなさん、全力を尽くして、がんばってください!
<参考リンク>
・ワインエキスパート 呼称資格認定試験:勉強方法
・ボルドーの等級格付け メドックの格付け(1855年) 1級-2級
・シニアワインエキスパートの認定バッジが届きました!
・ワインエキスパート二次試験用の資料(テイスティングシート)
・ワインエキスパート二次試験 ブラインドテイスティングのコツ
・「ソムリエ・ワインアドバイザー・ワインエキスパート 日本ソムリエ協会教本 2011」電子教本
・イーエックスワイン 品種別ハーフセット 12本
・Winaroma(ワイナロマ:香りのサンプル)
分厚い教本を読み込んでの、最後の追い込みに入っている事かと思います。
少しでも役に立ちそうな情報をまとめてみました。
右の写真はシニアワインエキスパートのバッジですが、デザインは同じみたい。
このバッジが届いたときは感無量です。みんながんばれ! p( ̄0 ̄)/
■教本は一通り目を通すべし!
試験内容は、教本の内容がそのまま出るパターンが多いので、分厚い本ですが、一通り目を通しておく必要があります。
ただ、それではポイントが分かりにくいので、参考書も別に購入してポイントを重点的に覚える事も必要ですね。
<参考書例>
◇ワイン受験講座 2012
私の受験時(2005年版)はA5サイズで持ち運びやすく、会社の行き帰りにずっと勉強してましたが、今はB5サイズでちょっと大きめですね。
A5サイズだと以下のテキストもあります。
◇改訂新版 30日間ワイン完全マスター2012 (Winart Book)
この参考書は、コンパクトに良くまとまっていて、分かりやすいですね。 (⌒_⌒)
残り少ない休日はじっくりと教本を読み込んで、平日は参考書を持ち歩いてどこでも勉強、というパターンはいかがでしょう。
■過去問題は必ずやること! ( ̄‥ ̄)/
過去問題が出る確率はかなり高いので、必ずやっておく必要があります。
日本ソムリエ協会の会員になると、ホームページで過去問題のPDFをダウンロードできるので、オススメです。
http://www.sommelier.jp/
入会金・初年度年会費は25,000円ですが、8月入会だと月割で安くなって、16,250円。
来年以降の年会費は15,000円です。(値上げしなければね)
ちなみに、会員は合格発表をホームページで確認できますね。
ワインセミナーなどにも参加出来て、情報ぎっしりの機関紙も隔月で届きます。
その他にも、過去の試験問題をまとめた本もあります。
◇改訂新版 ワインの過去問400 ソムリエ、ワインアドバイザー、ワインエキスパート呼称資格認定試験過去問題と解説でワインを学ぶ (Winart Book)
◇田辺由美のワインノート〈2012年版〉ソムリエ、ワインアドバイザー、ワインエキスパート認定試験合格のための問題と解説
「田辺由美のワインノート」はワイン呼称資格認定試験ではバイブル的な存在ですね。
私も買いましたが、あまりに問題数が多くて、全部は出来ませんでした・・・
( ̄∇ ̄*)ゞエヘヘ
■短期間で頭にたたきこむ!
ワインエキスパート試験は、とにかく記憶するものが多くて大変。
さまざまな方法でアクションしながら覚える事も重要ですね。
私の場合、どうしても覚えにくいものは単語帳を使って、常に持ち運んで見ていました。
自分で書き込む、というアクションも記憶につながります。
こういった本もあるんですよね、私は使いませんでしたが。
◇ワイン受験ゴロ合わせ暗記法〈2011〉
「ムートンは一級並(1973年)と言われていた天才(ピカソ)。」
シャトー・ムートン・ロートシルトが1級に格上げされた年とそのラベルの画家ですね。
なるほど、これは覚えるかも。 ( ̄∧ ̄)ふむふむ
試験はもう目前、あとはやるしかありません。
みなさん、全力を尽くして、がんばってください!
<参考リンク>
・ワインエキスパート 呼称資格認定試験:勉強方法
・ボルドーの等級格付け メドックの格付け(1855年) 1級-2級
・シニアワインエキスパートの認定バッジが届きました!
・ワインエキスパート二次試験用の資料(テイスティングシート)
・ワインエキスパート二次試験 ブラインドテイスティングのコツ
・「ソムリエ・ワインアドバイザー・ワインエキスパート 日本ソムリエ協会教本 2011」電子教本
・イーエックスワイン 品種別ハーフセット 12本
・Winaroma(ワイナロマ:香りのサンプル)
登録:
投稿 (Atom)
閲覧数の多い記事
-
<2017年8月22日> 2016年の二次試験結果発表では、選択項目までは開示されませんでした。 出題された品種のみですので、これはまた別途お知らせします。 どのような選択項目が出されたかは不明ですね~。 大きな変更は無いとは思いますが、最新の情報はワインスクールなどに...
-
ルイ・ド・ボーモン シャブリ 2014 Louis de Beaumont Chablis 2014 フランス:ブルゴーニュ地方:A.O.C.シャブリ アルコール度:12.5% ブドウ品種:シャルドネ OKストアで、税抜き1392円で購入。 【外観】 清澄度:...
-
ワインセラー 18本収納 ペルチェ式 上下段別温度設定 PWC-502P-B メーカー:アイリスオーヤマ 価格:17,300円(税込み) 【冷却方式】ペルチェ式 【最大収納本数】18本 【温度設定(環境温度:25℃)】上段:8~18℃:下段:10~18℃ 数...
-
Winaroma ワイナロマ 製造元:コーケン香料株式会社 購入先: ワイン・アクセサリーズ・クリエイション 価格:21420円 ワインの資格試験前に購入した香りのサンプル、「Winaroma」です。 香りのサンプルが小瓶で54本、30本分の試香紙が3セット、説明...
-
いままで、ワインは飲みきってしまうことが多く、余ったら料理用にして、ワインの保存はあまり気にしていませんでした。 でも最近、年齢とともにワインが多めに残るようになってきたので、ワイン保存のパイオニア、「バキュバン」を購入。 で、ホントに効果があるのか、早速テストしてみました...